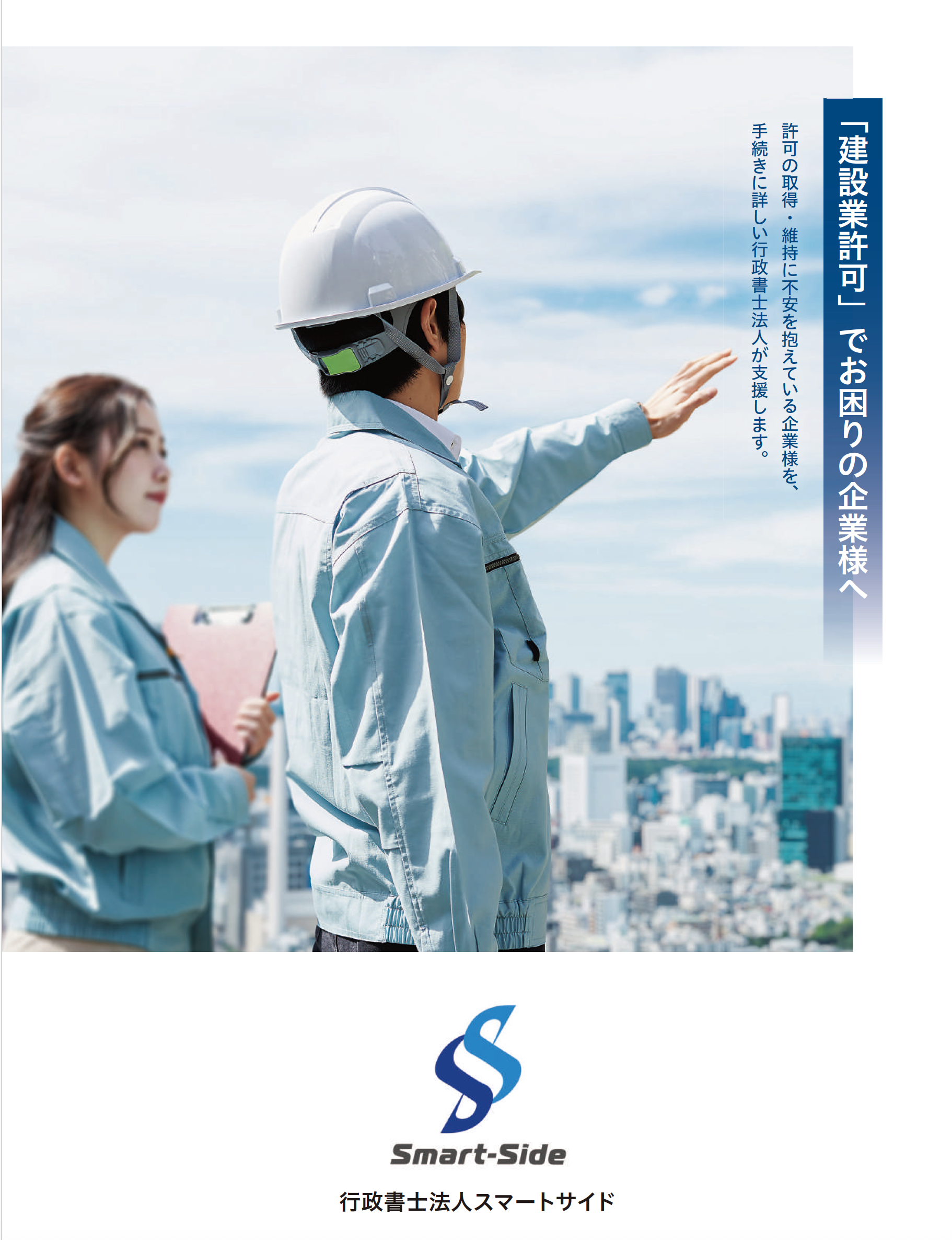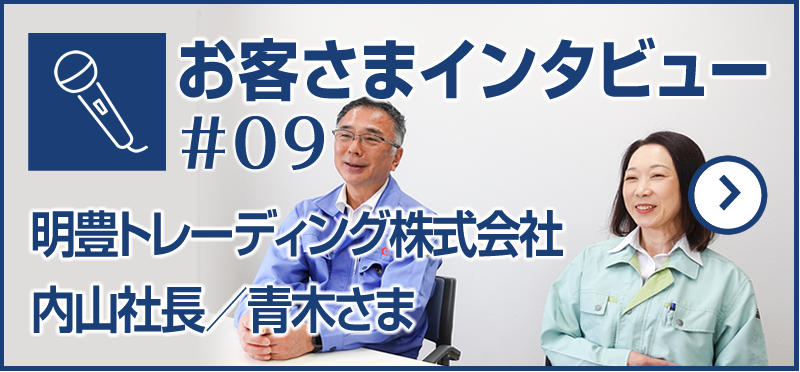建設業許可をすでに取得している会社でも、「新たな業種で許可が必要になった」「取引先から、ぜひ、他の業種でも許可を取得して欲しいと頼まれている」といったように、「業種追加」という選択が必要になることがあります。しかし、いざ申請しようと思っても「どんな書類が必要なのか」「営業所技術者は、どんな要件を満たしていればよいのか」など、実務上でつまずく点は多く、正確な情報を見つけるのも簡単ではありません。
本インタビューでは、これまで多数の建設会社の業種追加をサポートしてきた行政書士法人スマートサイド代表・横内賢郎が、実際の現場でよくある疑問や、スムーズに申請を通すためのコツについて詳しく語ります。「業種追加ってそもそも何?」「うちの会社でもできる?」といった初歩的な疑問から、申請を成功させる5つの実践的ポイントまで、専門家ならではの視点で丁寧に解説しています。
これから業種追加を検討している方や、手続きに不安を感じている方にとって、本記事が最初の一歩となるはずです。
「建設業許可の業種を増やすこと」=「業種追加申請」
それでは、横内先生。本日も、よろしくお願いします。
こちらこそ、よろしくお願いします。本日のテーマは、業種追加申請についてですね。

まず、業種追加申請について、簡単に説明すると、すでに持っている建設業許可の業種を増やすことを業種追加と言います。そして、その際に必要になる申請が業種追加申請です。
たとえば、
- すでに持っている管工事の建設業許可に、電気工事の建設業許可を追加する
- すでに持っているとび工事の建設業許可のほかに、内装工事の建設業許可も取得する
といったようなイメージです。「建設業許可を取得した際には必要性を感じてなかった業種」や、「建設業許可を取得した際には取得することができなかった業種」について、あとから、あらたに建設業許可を取得する手続きと言い換えることもできます。
今日は、その業種追加申請について、実務上の観点から5つのポイントをお話しいただけるわけですね。
はい。5つのポイントをお話しさせて頂きます。
まず、1つ目は、業種追加申請には、「5万円の手数料がかかる」という点です。建設業許可を新規で申請した際には、許可行政庁に支払う手数料は9万円でした。また、5年に1度、建設業許可を更新する際に、かかる手数料は5万円です。許可業種を増やすための業種追加申請の際にも、許可行政庁に支払う手数料として5万円の手数料が必要であることを、覚えておいてください。
ちなみに、1業種追加する場合でも、10業種追加する場合でも、手数料は5万円です。追加する業種の数によって、変動はしません。
営業所技術者の常勤性
業種を追加する際には、営業所技術者が必要であると聞いたことがあります。
はい。業種追加申請をするうえで、営業所技術者の要件の理解は、必須です。
2つ目のポイントとして、営業所技術者は、常勤でなければなりません。つまり、内装工事を追加したいのであれば、内装工事の営業所技術者の要件を満たす人が、会社に常勤していなければ、内装工事を業種追加することができません。管工事を追加する場合でも、とび工事を追加する場合でも、同様に、該当の工事の「営業所技術者の要件」を満たす人が、会社に常勤していることが必要です。
この常勤性を証明するための資料が「健康保険証のコピー」であったり「健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書」であったり「住民税の特別徴収通知書(納税義務者用)」であったりします。会社に雇用され、その会社からきちんと給料が支払われて、その給料から社会保険料や住民税が支払われているという関係性にあることが必要です。
たとえば、2級建築士は、「建築工事」「屋根工事」「大工工事」「タイル工事」「内装工事」の営業所技術者になることが可能です。そのため、「とび工事」の建設業許可を持っている会社が、2級建築士を社員として雇用した場合、もしくは、社内に2級建築士に合格した人が現れた場合、いま持っている「とび工事」に「建築工事」「屋根工事」「大工工事」「タイル工事」「内装工事」の5つの業種を追加することができるようになるのです。
私の事務所では、実際に「二級土木施工管理技士の資格を使って、とび工事の建設業許可に6つの業種を追加した」実績があります。
資格者がいない場合の「業種追加申請」の注意点
なるほど、資格者がいると許可が取りやすいというのは、新規申請の時と同じですね。それでは、資格者がいないときの注意点などはありますでしょうか?
営業所技術者になるには
- (1)該当の資格を持っていること
- (2)特殊な学科を卒業後、3~5年の実務経験があること
- (3)10年の実務経験があること
のいずれかに該当しなければなりません。
この点については、以前のインタビュー記事でも詳しく解説していますので、よくわからないという人は、そちらの記事(※注)も参考にしてみてください。
(注)【専門家に聞く】営業所技術者の要件とは何か?建設業許可取得に不可欠な知識を実例解説
(1)の「資格者」に該当する人がいなければ、3~5年もしくは10年の実務経験を証明する必要があります。ここでの、業種追加申請の3つ目のポイントは、「実務経験期間は重複して使用することができない」という点です。
「実務経験期間を重複して使用することができない」というのは、どういう意味ですか?

たとえば、内装工事の営業所技術者のAさんがいたとします。Aさんは、10年の内装工事の実務経験を証明して、内装工事の営業所技術者として認めてもらうことができました。この場合、この10年は「内装工事の実務経験期間」として使用済みであるため、別の工事の実務経験期間として使用することができないのです。
仮にA建設会社が、社長であるAさんの「××21年~××30年」の間の10年間の内装工事の実務経験期間を使用して、内装工事の建設業許可を取得した場合、このAさんの「××21年~××30年」の間の10年間は、別の工事の経験として使用することができません。そのため、A建設会社が、とび工事を追加しようと考えた際には、Aさんの「××31年~××40年」の10年間のとび工事の実績を証明するか、もしくは、Aさん以外の人を営業所技術者にして、とび工事を業種追加するしかないのです。
Aさんの内装工事で使った10年は、他の工事の実績として使用することができないのですね。
はい。A建設会社が内装工事の建設業許可を取得する際に使用したAさんの10年の実務経験期間は、他の工事の実績として使用することができません。一方で、A建設会社にBさんという人がいて、そのBさんの実績であれば、同じ「××21年~××30年」の間の10年間の実績を別の工事の実績として使うことができます。
このあたりの理解は非常に難しいのですが、「実務経験は属人的にカウントする」という風に理解して頂くとよいのではないかと思います。Aさんが内装工事で使った10年は、別の工事の実績があったとしても、別の工事の証明期間に含めることができません。しかし、一方で、同じ会社に属しているBさんがいれば、仮に、Bさんの実務経験期間が、Aさんが内装工事で使った10年と被っていたとしても、問題なく別の工事の実務経験期間としてカウントすることができるのです。
「業種追加申請」と「決算変更届」との整合性の問題
「実務経験は、属人的にカウントする」ということですね。他に業種追加申請の際に、気を付けなければならない点はありますか?
はい。実は、業種追加申請の際に、一番気を付けなければならないポイントは、決算変更届の際に提出している「直前3年の各事業年度における工事施工金額」という書類との整合性です。
まずは、この書類をご覧ください。

この書類は、決算変更届の際に提出している「直前3年の各事業年度における工事施工金額」という名前の書類です。この会社が、仮に、管工事を業種追加したいと検討している場合、この書類のどこに問題があるか?わかりますか?
内装工事の売上は、第9期が5000万円、第10期が6500万円、第11期が7000万円と、右肩上がりで増えているので、特に問題がないように思えます。
おっしゃる通り、内装工事の実績は、特に問題ありません。しかし、この会社は、内装工事に管工事を業種追加したいと考えている会社です。それにも関わらず、「その他の建設工事の施工金額」が、3期とも「0円」になっています。この会社に、管工事施工管理技士などの資格者がいて、その資格者を営業所技術者にして、管工事を追加するのであれば、特に問題ありません。
しかし、この会社に資格者がおらず、管工事の実務経験を使って、営業所技術者要件を証明する場合にはどうでしょう?この会社は、これから管工事の建設業許可を取得するべく、管工事の実績を証明していかなければならないにも関わらず、「その他の建設工事の施工金額」が「0円」になっているということは、「内装工事以外の実績はありませんでした」と言っているのと同じです。
「内装工事以外の実績」つまり「管工事の実績」がないので、この会社は、仮に、会社として管工事の実績を積んでいたとしても、書類上、管工事の実績を証明することができなくなってしまいます。『「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の「その他の建設工事の施工金額」が0円になっているという事実』と、『過去において内装工事以外の工事の実績がありましたという事実』は、矛盾してしまいますので、整合性が取れないのです。

このように、業種追加申請をする場合には、決算変更届の際に、どういった金額の割振りをおこなって届出を提出しているのかが、非常に重要になってきます。東京都の場合には、「別紙8の訂正」という書類を提出することによって、過去に提出した決算変更届の記載を訂正することは可能です。しかし、「その他建設工事の施工金額」が「0円」になっている場合には、いまお伝えしたような不都合があることを理解しておいてください。
「その他の建設工事の施工金額」が0円になっているからと言って、業種追加をあきらめなければならないかというと、そういうわけではありません。弊所の経験上、東京都の場合ですが、「別紙8の訂正」という書類を提出することによって、金額自体の訂正は可能です。実際に、「別紙8の訂正」を行って、金額訂正後に、業種追加をすることができた事例がありますので、「業種追加できない」ということはありません。
しかし、申請書類の作成の難易度が、一気にあがり、ハードルが高くなることは、十分に理解しておいてもらったほうが良いと思います。
ご説明ありがとうございます。それでは5つ目のポイントは、何でしょうか?
4つ目のポイントと関連してくるのですが、5つ目のポイントは、実務経験の証明の方法に関してです。資格者がいない場合、長かれ短かれ実務経験の証明が必要になってきます。
とび工事を追加したいのであれば、とび工事の実務経験の証明が必要です。管工事を追加したいのであれば、管工事の実務経験の証明が必要です。そして、これらの証明は「工事請負契約書」「工事注文書」「請求書+入金記録」のいずれかで行わなければなりません。この点については、以前のインタビューでもお話ししているので、時間の関係上、今回は、割愛させて頂きます。
もし、「工事請負契約書」「工事注文書」「請求書+入金記録」での実務経験の証明方法を知りたい人がいれば、過去のインタビュー記事(※注)を参考にしてみてください。
(注)【専門家に聞く】営業所技術者の証明書類、どこまで揃えれば大丈夫?実務のポイントを解説
新規で許可を取得するときと同様に、やはり、実務経験を証明するには「請求書や入金記録」といった証明資料が必要になってくるのですね。
はい。
「工事請負契約書」がなければ「注文書」、「注文書」がなければ「請求書と入金記録」という証明方法は、「マスト」といってよいでしょうね。結局、「業種追加申請がうまく行くかどうか?」は、こういった実績証明のための書類を、どれだけスピード感を持って揃えることができるか否かにかかってくるのだと思います。
そういった意味で、やはり、専門家の力を借りて、「どういった書類をどの程度の割合で準備すべきか?」という点について、アドバイスを受ける、もしくは、手続きをすべてお願いするということが、業種追加の近道であるように思います。
ありがとうございます。それではお時間になりましたので、最後に一言お願いいたします。
業種追加の手続きは、「どの業種を追加すべきか」から始まり、「営業所技術者の条件」「決算届との整合性」など、考えるべきことが多く、初めて取り組む方にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。とくに、過去の実務経験をどう証明するか、社内で誰を営業所技術者に据えるかといった判断は、経営者として慎重に行う必要があります。
ですが、今回お話ししたように、正しい知識と段取りさえ押さえておけば、業種追加は決して不可能な手続きではありません。むしろ、自社の強みを活かし、新たな工種に挑戦する第一歩として、有効な選択肢となるはずです。
この記事が、業種追加を検討されている皆さまの一助となり、次の一歩を踏み出す後押しになれば幸いです。