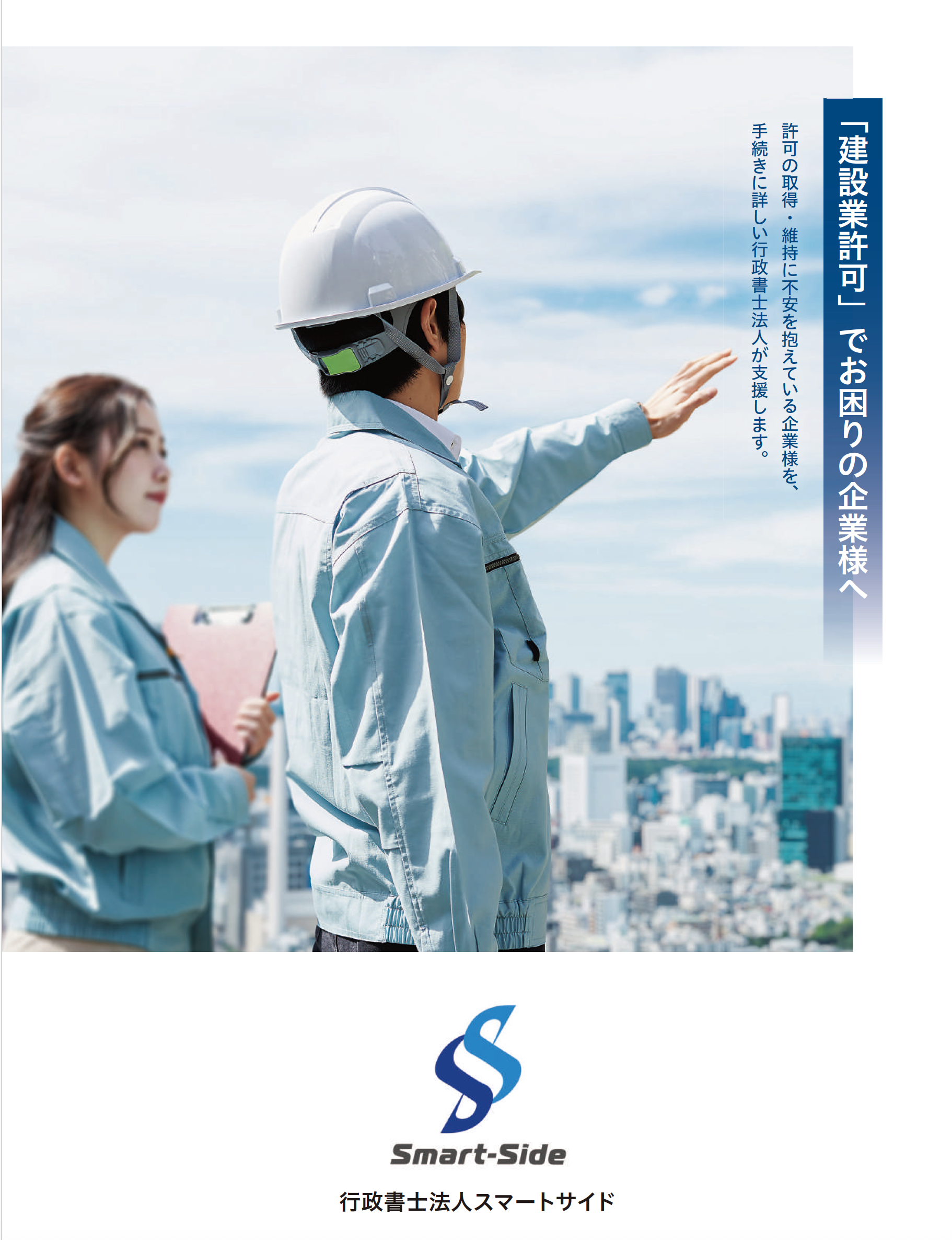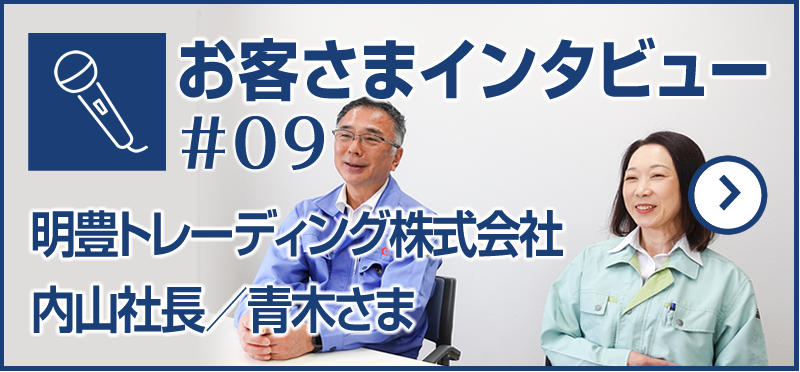東京都で建設業許可を取得したいと考えたとき、まず悩むのが「そもそも、建設業許可を取ることはできるのか?」「建設業許可の要件を満たしているのか?」「申請書類は、どのようなものを用意すればよいのか?」「実績・経験の証明は、どうすればよいのか?」といった不安です。特に初めて許可を取得する会社にとっては、「制度の仕組み」や「東京都の判断基準」がわかりづらく、どこから手を付けてよいか分からないという声を多く聞きます。
本インタビューでは、東京都における建設業許可申請の実務に精通し、数多くの建設会社をサポートしてきた専門家――行政書士法人スマートサイドの代表・横内先生に、「行政書士として、どのように許可取得を成功に導いているのか」「今なぜ専門的な支援が必要とされているのか」を詳しくお話ししてもらいます。――その答えを、ぜひ本文でご確認ください。
建設業許可取得のトレンド
それでは、横内先生。よろしくお願いします。
はい。こちらこそ、よろしくお願いします。
今日は、「東京都の建設業許可を確実に取りたい」と考えている人に向けて行政書士選びのポイントとともに、私が感じる「建設業許可取得の現状」ついて、触れていきたいと思います。特に最近になって感じる「ホットな話題」「最新トレンド」をお話しできればと思いますので、建設業許可の取得および行政書士選びで困っている人は、ぜひ、最後まで、お付き合いただければと思います。

最近増えている「建設会社以外の会社」からの許可取得の相談
最新のトレンドですね。とても興味があります。早速、続きをお願いします。
はい。最近になって顕著な傾向として、まず、挙げられるのは、「建設会社以外の会社から建設業許可取得の相談が多い」という点です。以前であれば、土木工事や建築工事などの建設業を専門に行っている会社が、「現場に入るため」とか「取引先からの要望があって」という理由で、建設業許可を取得することが、ほぼ100%でした。
ところが、最近は、「イベント企画運営会社」「デザイン設計会社」「不動産開発業者」「設備製造会社」など、いわゆる建設業以外の業務を主たる業務としている会社からの相談や許可取得のご依頼が増えて来ているように思います。
こういった会社の中には、「取引先」や「元請」から、建設業許可を取得するように指示を受けて許可の取得を検討するような会社もあります。しかし、一方で、同業他社との差別化や競争優位性を確保するために、自ら積極的に、建設業法を勉強し、許可取得に挑戦しようという意欲にあふれた会社が多いイメージです。たとえば、先日も、大手の「イベント会社」からの許可取得のご依頼がありました。その会社は、「500万円以上の工事を請負うのは、年に数回しかない。けれども、コンプライアンスや会社の将来のことを考えて、ぜひとも、今のうちに建設業許可を取得しておきたい。」という理由で、弊所に手続きをご依頼頂いた経緯があります。
このように、以前では、建設業許可を取得するのは建設会社が多かったのですが、最近では、成長意欲にあふれた異業種の会社から建設業許可の取得手続きのご依頼・ご相談を受けることが、非常に増えている印象です(※注)。
(注)【専門家に聞く】建設会社でなくても建設業許可が必要?よくある誤解と許可取得の方法
建設会社以外の会社でも、建設業許可は取得できるものなのでしょうか?
はい。建設会社以外の会社でも建設業許可を取得することは可能です。
ただし、経営業務管理責任者の経営経験や、営業所技術者の実務経験の証明に苦労することが多いです。建設会社であれば、「建設業の経営経験」「建設工事の実務経験」は、比較的簡単に証明できるのですが、「建設業がメインでない」となると、なかなか、過去の工事の経験を証明しづらいのが現実です。

やはりその点については、依頼を受けた行政書士の力量というか、経験値がものをいう世界だと思います。「経験・実績がないから、建設業許可をあきらめるしかない」と考えるのか、それとも「別の書類を準備することによって、許可取得の可能性がある」と考えるのか。会社の置かれた状況に応じて、許可取得のための提案をできるかどうかが、とても大事な要素になってきます。
執行役員を経営業務管理責任者にして建設業許可を取る方法
なるほど、「別の提案ができるかどうか?」が、行政書士選びのポイントになるのですね。他には、最近のトレンドみたいなものは、ありますか?
はい。最近、うちの事務所で特に力を入れているのが、「執行役員を経営業務管理責任者にして建設業許可を取る方法」です。
令和2年に建設業法が改正された当時は、「建設業許可が取りやすくなる…」という期待がありました。しかし、蓋を開けてみると、「許可を取りやすくなった」ということはなかったのです。そのような中でも、許可行政庁によっては、「執行役員を経営業務管理責任者にして、許可取得を認める」ことについて、比較的柔軟に対応してくれている印象があります。
執行役員を経営業務管理責任者にすると、どういった利点があるのすか?
はい。
本来であれば、経営業務管理責任者になるには、取締役としての経験が5年以上必要です。この「取締役としての5年以上の経験」を満たすことができずに、建設業許可取得をあきらめざるを得ない企業はたくさんあります。例えば、「取締役に就任してから3年しか経っていない」とか「会社設立後、2年しか経過していない」という理由で「5年」という期間を満たすことができない会社が多いのです。
そんな中、取締役ではなく、執行役員のポジションで経営業務管理責任者になれるとすると、執行役員として5年以上の経験があれば、要件を満たすことになります。そのため、建設業許可を取得する可能性が、広がるのです。
これは「建設業許可の取得が簡単になる」という意味では決してありません。むしろ、執行役員を経営業務管理責任者にして建設業許可を取得するのは、とても難しい作業です。「組織図」や「業務分掌規程」や「取締役会規則」がなければなりませんし、「取締役会議事録」も必要になってきます。そのうえ、これらの書類があるだけでは足りず、書類同士の整合性も取れていなければなりません。
ここでは詳細は割愛しますが、「執行役員が経管になることができる」イコール「建設業許可を取得しやすくなった」というわけではないので、決して勘違いをしないようにして頂きたいです。ただ、弊所では、そういった方法を用いて、建設業許可を取得したケースが何件もあります(※注)。
(注)取締役ではない執行役員を経営業務管理責任者にして、東京都の建設業許可を取得した事例を詳細解説
執行役員を経管にして許可を取得する方法は、実務の経験と専門性が無いと、難しいと言わざるを得ません。そういった意味で、やはり、「建設業許可取得の手続きを、どの行政書士に依頼するのか?」という点が重要になってくると思います。
「建設業許可専門」を売りにしているだけでは判断できない
やはり、ここでも「どういった行政書士事務所に依頼するか?」が許可取得にとって重要になってくるのですね。
はい。
「スムーズに建設業許可を取得することができるか?」それとも「長期間にわたって手こずるか?」は、行政書士事務所選びに掛かっているといっても、過言ではありません。私は、建設業許可の申請手続きを専門にして、もう10年以上が経ちます。ですが最近は、「建設業許可専門の行政書士です」と名乗るだけでは、お客様に選んでいただける理由にはならない時代になってきたと感じています。
行政書士事務所の中には、経験の浅い人や、専門知識のないまま「建設業許可専門」や「業界最安水準」をアピールし、一生懸命に集客している事務所もあるようです。もちろん、そういった事務所の中には、優れた実績を持っているところもあります。一方で、専門的知識や経験が乏しいところも少なくありません。
そういった事務所を見分けるには、どうすればよいのでしょうか?
まずは、ホームぺージを詳細に読んでみることをお勧めします。「実績があるのか?」「お客さまの声が掲載されているのか?」「専門家としての解説記事があるのか?」というように、ホームぺージを読み込むことによって、その事務所が信頼に値するか、判断することができると思います。(※注)
あとは、実際に、相談をしてみるという手もあります。相談をしてみて、適確な回答が返ってくるのか?すぐに返信をくれるのか?という点も重要になってくると思います。
行政書士法人スマートサイドのアピールポイントは?
ところで、横内先生の事務所は、「建設業許可取得の専門家」として、どういったアピールポイントがあるのでしょうか?
はい。私たちの事務所のアピールポイントは、「比較的、規模の大きい会社からのご依頼」や「複雑で難しい案件」を得意としている点にあります。

たとえば、弊所のお客さまの中には「売上規模として100億円以上」「従業員人数が100名以上」という大規模会社もいらっしゃいます(※注)。誰もが知っている有名グループ企業の子会社もあります。また、難しめの案件で言うと、「執行役員を経管にして建設業許可を取得」」「10年の実務経験の証明に成功」「出向役員を経管することに成功」「実務経験期間の短縮に成功」とさまざまな実績を持っています。
「他の行政書士事務所に依頼したけど、無理だったので、スマートサイドさんにお願いしたいです」という会社もあるくらいです。
(注)【専門家に聞く】全国30拠点以上の建設会社に学ぶ|令3条の使用人と営業所技術者の管理・変更届の実務
なるほど。まさに、建設業許可取得の専門家ですね。仮に、建設業許可取得の手続きを行政書士法人スマートサイドに依頼したい場合には、どうすればよいのですか?
はい。弊所では、事前予約制の有料相談を実施しています。
以前は、無料相談を行っていた時期もあったのですが、本当に建設業許可の取得に向けて真剣に取り組んでいる方に、確実で丁寧なサポートをご提供するため、現在は有料相談という形を取らせていただいております。限られた時間のなかで、一つひとつのご相談にしっかりと向き合い、具体的なアドバイスや対応策をご提示できるようにするための判断です。
弊所に建設業許可の手続きを依頼したいという人には、ホームページにある問い合わせフォームからメールにてご連絡いただくようにご案内しています。
電話での連絡は、ダメなのですか?
はい。電話でのご連絡は、承っておりません。弊所には、複数の専門スタッフが在籍しており、そのスタッフ同士で情報の共有をよりスムーズに行うために、電話ではなく、メールでのご連絡をお願いしています。また、メール・文章でやり取りすることによって、安心感と正確性を担保できるばかりでなく、お客さまに対して「待ち時間のない迅速で確実な対応ができる」というメリットを感じています。
そのため、弊所への連絡は、電話ではなく、すべてメールにてお願いをしている次第です。
実際に、有料相談を申し込んだ場合、どういったことをしてくれるのですか?
はい。
まずは、お客さまが建設業許可を取得できる可能性があるかどうか、専門家として正確に判断させていただきます。これまで多くのご相談をいただいてきましたが、なかには建設業許可の要件や手続きについて、まったく情報をお持ちでない人もいらっしゃいます。どれだけ許可取得を強く望んでも、現時点で法的な要件を満たしていない場合には、許可の取得が難しいという判断になることもあります。
しかし、そのような場合でも、ただ「できない」とお伝えするのではなく、将来的にどうすれば許可取得が可能になるのか、どのような準備が必要なのか、いつ頃から申請できそうかといった点について、的確かつ実務的なアドバイスをご提案させていただきます。
また、「執行役員を使って許可が取れないか」「社員の学歴を使って許可が取れないか」など、さまざまな方法を検討させて頂きます。その流れで、許可取得の手続きを弊所にご依頼くださるお客さまがほとんどです。
建設業許可を取得したいとお考えのみなさまへ
それでは、お時間になりましたので、最後に、建設業許可を取得したいと考えている人へ、ひとこと、お願いできますでしょうか?
建設業許可の取得手続きは、非常に難しい手続きと言って良いと思います。もちろん、自ら行政に確認をしたり、インターネット検索で情報を収集したりして、専門家の手を借りずに、建設業許可を取得したいと考えている人もいるでしょう。
しかし、時間がかかるばかりでなく、証明方法を間違えると、建設業許可を取得することができません。都庁に書類一式を持参したけど、受付してもらえなかったという話は、よく聞きます。
とくに、経営業務管理責任者や営業所技術者の証明、過去の工事実績の整理、決算書類の読み解きなどは、専門的な知識が求められる場面です。「自分でできる」と思っていたけれど、途中で立ち止まってしまい、結局は何カ月もかかってしまったというご相談も珍しくありません。建設業許可は、ただ取得することが目的ではなく、その先にある「仕事の受注」や「信頼の獲得」にこそ価値があります。だからこそ、確実に、そしてスムーズに進めることが何より重要です。
もし少しでも不安や疑問を感じていらっしゃるのであれば、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。それが、結果として最短で許可を得る近道になることも多いのです。
これから建設業許可の取得を目指す方にとって、このインタビューの内容が、手続きへの不安を和らげ、具体的な道筋を見つけるきっかけとなれば幸いです。建設業許可は、単に書類を整えるだけの手続きではなく、事業の未来を左右する大切な一歩です。だからこそ、正確な情報と適切な判断が不可欠なのです。
この記事が、許可取得への第一歩を踏み出す助けとなり、今後の事業展開に少しでも貢献できたなら、専門家としてこれほど嬉しいことはありません。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。