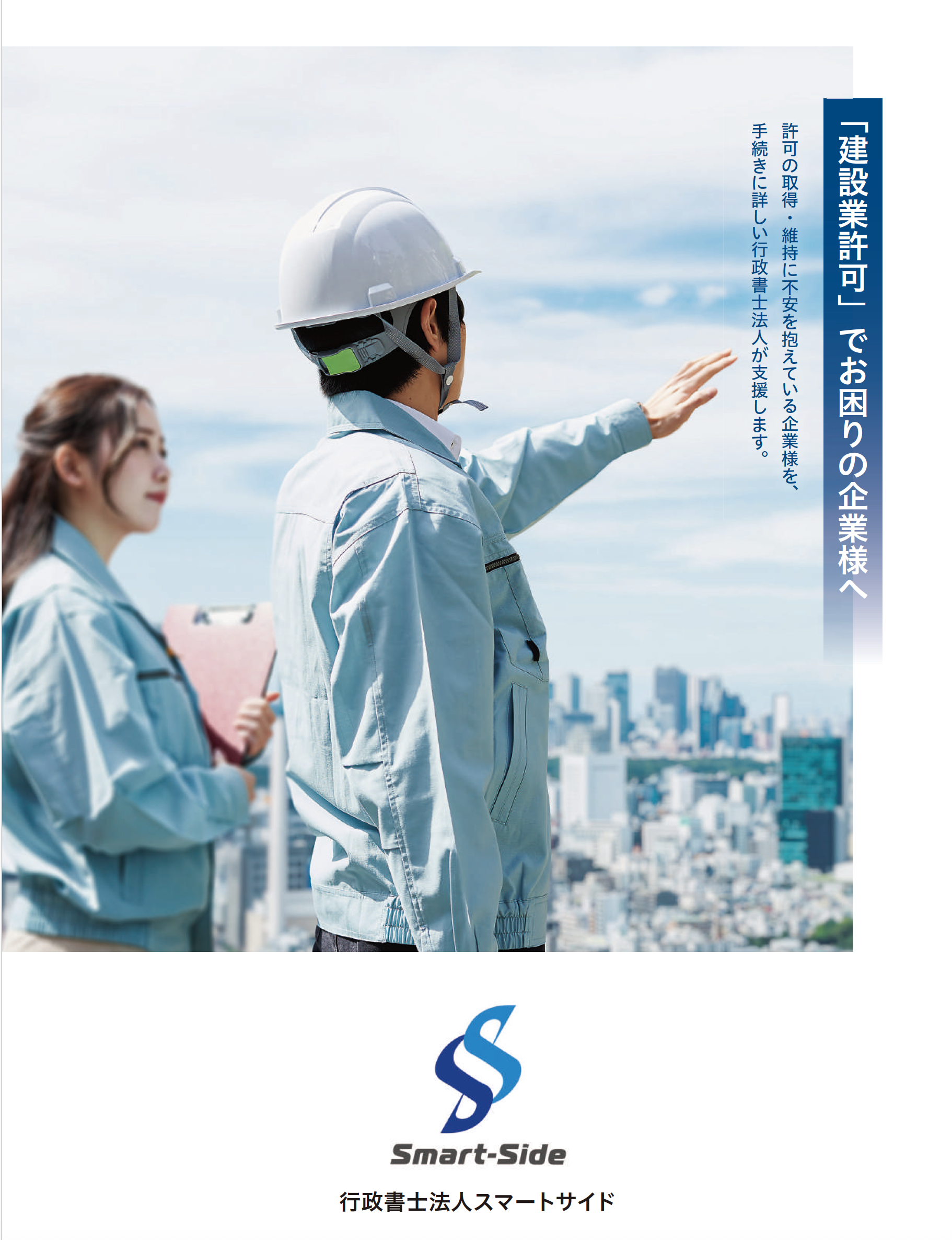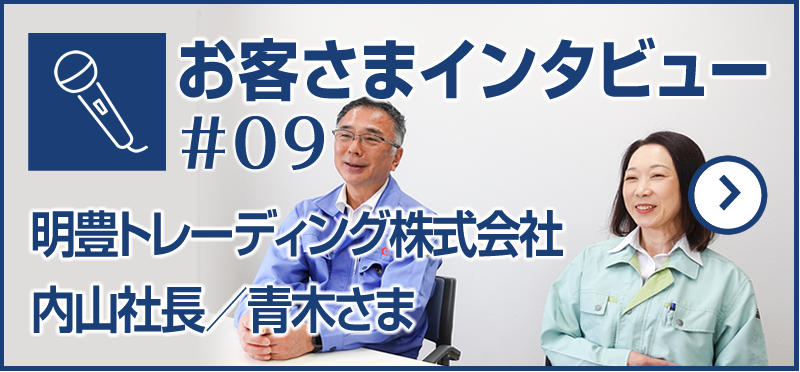建設業許可を取得するためには「専任技術者」の常勤が必要です。専任技術者になるには、施工管理技士などの国家資格があると便利ですが、国家資格がなくても、専任技術者になることができます。
仮に、施工管理技士などの国家資格がなくても
- 「10年の実務経験」を証明する方法
- 「指定学科の卒業経歴」+「3~5年の実務経験」を証明する方法
のいずれかで、専任技術者になることができるのです。
今回は、「大学の機械工学科の卒業経歴」+「3年の実務経験」を証明して、管工事の建設業許可を取得した事例のご紹介です。たまたま、従業員(社員)の中に、大学の機械工学科を卒業した方がいましたが、この方がいなければ、社長の10年の実務経験の証明をしなければならない事案でした。
建設業許可を取得する際の、専任技術者の要件の証明の仕方は、とても複雑です。このページで紹介する事例を通して、国家資格を持っていない人の専任技術者の要件の証明方法を学んだ頂ければ幸いです。
相談内容:管工事の建設業許可を取得しなければならない!
概要
| 会社所在地 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 業種 | 管工事 |
相談内容
| 相談内容 | 空調設備や給排水設備の販売、設置、メンテナンスなどを行っている。設置工事自体の金額が500万円以上になることは、滅多にないが、設備の販売・備え付け・設置工事といった一連の価格を合わせると500万円を超えるため、管工事の建設業許可が欲しい。 |
|---|
申請内容
| 申請内容 |
|
|---|
行政書士法人スマートサイドの対応
管工事をメインで行っているというよりは、空調機器や給排水機器の「販売」をメインで行っている会社でした。管工事の占める割合は全売上のうち1~2割程度ということです。
売上に占める工事の割合が1~2割だからといって建設業許可を取得しなくてよいわけではありません。「工事の請負金額」が、税込み500万円以上になる場合はもちろんのこと、仮に「工事の請負金額」が、500万円未満であったとしても、「空調機器や給排水設備の販売価格と工事代金を合計した金額」が、税込み500万円以上になる場合には、建設業許可の取得が必要になります。
この会社の場合、ほとんどの工事代金は数十万円程度に収まっていましたが、年に何件かの割合で、販売費用と工事代金の合計が数百万円になってしまうような工事があるとのことでした。そこで、弊所としても、建設業許可取得が必要であると判断し、受任する運びとなりました。
なお、お客様は弊所にご相談に来る前に、自ら都庁に相談に行ったらしいです。しかし、
- 担当者によって言っていることが違う
- 前に言っていたことと今言っていることが違う
など、対応に疑問があったそうです。そこで「こういったことは専門家に任せた方が良い」といった理由で弊所を選んでいただいたそうです。
管工事の経営業務管理責任者の要件の2つのポイント
常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)の要件
(1)過去の経験年数の証明
建設業許可を取得するには、常勤役員等(旧:経管)の要件を満たす人がいなければなりません。この要件は、
- 取締役として5年以上の経験があること
- 個人事業主として5年以上の経験があること
といったように基本的には5年以上の取締役もしくは個人事業主としての期間が必要とされます。
このお客様の場合、設立から30年以上の社歴があり、しかも、現社長が取締役に就任したのは、平成7年6月です。そのため「取締役として5年以上の経験があること」といった要件を満たします。
これで(1)はクリアです。
(2)建設業を経営していたことの証明
(1)をクリアできたとしても、取締役であった5年以上の期間、「建設業を経営していたこと」を証明することが必要になります(2)。
この建設業を経営していたことを証明する資料として挙げられるのが
- 工事請負契約書
- 工事請書+注文書
- 請求書+入金通帳
といった資料になります。この1~3のいずれかの資料を、ひと月につき1件以上、用意しなければなりません。5年間の「建設業を経営していたことの証明」に必要な資料の件数は、12か月×5年=60か月なので、60件以上の「工事請負契約書」などが必要になります。
この事案では、管工事の「3.請求書および入金通帳」を会社側で保管していてくださったので、「3.請求書および入金通帳」を60件分以上(5年以上)用意しました。
これにより、(2)もクリアできたことになります。
管工事の専任技術者の要件をクリアするには?
専任技術者の要件を確認!
続いて専任技術者の要件についてです。
「経営業務管理責任者の要件の2つのポイント」は比較的スムーズにクリアできたので、この申請の山場は、「常勤役員等(旧:経管)」ではなく「専任技術者の要件の証明」にあります。
そこで、専任技術者の要件についておさらいをしておくと、今回のように管工事の建設業許可を取得したい場合には、
- 管工事に関する試験の有資格者
- 管工事に関する指定学科の卒業+管工事の3~5年の実務経験の証明
- 管工事の10年の実務経験の証明
のいずれかを選択しなければなりません。
以下、具体的に見て行きます。
1.管工事の専任技術者になるための必要な資格
管工事の専任技術者になるための必要な資格は以下の通りです。
| 技術検定 |
|
||
|---|---|---|---|
| 技術士試験 |
|
||
| 民間資格 |
|
||
| 水道法試験 |
|
||
| 技能検定 |
|
||
| 基幹技能者 |
|
||
建築設備士や一級計装士などのように、試験に合格していても実務経験が必要な資格もありますので、注意してください。
なお、管工事施工管理技士の資格を持っていれば、実務経験の証明をすることなく、管工事の専任技術者になることが可能です。
2.管工事の専任技術者になるための必要な指定学科
「1」で見たような資格を持っていなかったとしても、諦める必要はありません。「1」に掲げた国家資格・民間資格を持っていなくても、特定の学科を卒業した経歴があれば、管工事の専任技術者になることが可能です。この特定の学科のことを指定学科と言います。
高校や大学で「土木工学」「建築学」「都市工学」「機械工学」「衛生工学」を専攻し、卒業されている方は、管工事の専任技術者になるための指定学科を卒業していることになるため、実務経験の証明期間が10年から3年もしくは5年に短縮されます。
以下は、指定学科の具体例です。
| 土木工学 | |||
|---|---|---|---|
| 開発科/海洋科/海洋開発科/海洋土木科/環境造園科/環境科/環境開発科/環境建設科/環境建設科/環境整備科/環境設計科/環境土木科/環境緑化科/環境緑地科/建設科/建設環境科/建設技術科/建設基礎科/建設工業科/建設システム科/建築土木科/鉱山土木科/構造科/砂防科/資源開発科/社会開発科/社会建設科/森林工学科/森林土木科/水工土木科/生活環境科学科/生産環境科/造園科/造園デザイン科/造園土木科/造園緑地科/造園林科/地域開発科学科/治山学科/地質科/土木科/土木海洋科/土木環境科/土木建設科/土木建築科/土木地質科/農業開発科/農業技術科/農業土木科/農業工学科/農林土木科/緑地園芸科/緑地科/緑地土木科/林業工学科/林業土木科/林業緑地科 |
| 建築学 | |||
|---|---|---|---|
| 環境計画科/建築科/建築システム科/建築設備科/建築第二科/住居科/住居デザイン科/造形科 |
| 都市工学 | |||
|---|---|---|---|
| 環境都市科/都市科/都市システム科 |
| 機械工学 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー機械科/応用機械科/機械科/機械技術科/機械工学第二科/機械航空科/機械工作科/機械システム科/機械情報科/機械情報システム科/機械精密システム科/機械設計科/機械電気科/航空宇宙科/航空宇宙システム科/航空科/交通機械科/産業機械科/自動車科/自動車工業科/生産機械科/精密科/精密機械科/船舶科/船舶海洋科/船舶海洋システム科/造船科/電子機械科/電子制御機械科/動力機械科/産業機械科 |
| 衛生工学 | |||
|---|---|---|---|
| 衛生科/環境科/空調設備科/設備科/設備工業科/設備システム科 |
実に様々な学科が掲げられています。今回弊所にご依頼いただいたお客様は、「大学」の「機械工学」の「機械科」を卒業されていました。
皆さんも当てはまるものがないか?ぜひ確認をしてみてください。
3.管工事の専任技術者になるための必要な実務経験の証明年数
「1」で掲げた管工事施工管理技士のような国家資格を持っている場合には、管工事の実務経験の証明は必要ありませんが、「指定学科卒業の場合」や「指定学科卒業の経歴がない場合」には、実務経験の証明をしなければなりません。
実務経験の証明期間は、ケースごとで異なりますので、以下の表を参考にしてください。
指定学科の卒業経歴ありの場合
| 高等学校 | 指定学科卒業+実務経験5年 | ||
|---|---|---|---|
| 中等教育学校 | |||
| 大学・短期大学 | 指定学科卒業+実務経験3年 | ||
| 高等専門学校 | |||
| 専修学校 | 指定学科卒業+実務経験5年
(専門士、高度専門士であれば3年) |
||
指定学科の卒業経歴なし
| 指定学科の卒業なし | 実務経験10年 | ||
|---|---|---|---|
この事案では「大学」の「指定学科」の卒業なので、実務経験の証明期間は3年ということになります。
もし仮に「高校」の「指定学科」の卒業であったのであれば、実務経験の証明期間は5年になります。
さらに、「指定学科」の卒業経歴がなければ、実務経験の証明期間は10年になります。
今回の申請で必要になった
専任技術者要件を証明するための資料は?
専任技術者の要件を証明するための資料
それでは、今回の事案で、専任技術者の要件を証明するために、実際にどのような証明資料をもって都庁に申請をしに行ったかを記載します。
(1)卒業証明書
卒業証明書は、卒業した大学に行って、発行してもらいました。申請の際には、原本を預かって、都庁まで持参しました。指定学科を卒業したことを証明するためには、卒業証明書の原本が必須になります。
(2)管工事の請求書+入金通帳
「大学の機械工学科」を卒業した場合の、実務経験の証明期間は3年です。上記にも記載した通り、通常であれば10年間の実務経験の証明が必要なところ、大学の指定学科の卒業という経歴によって、3年に短縮されます。
この3年間の実務経験の証明については、お客様に「管工事の請求書」+「入金記録」を用意してもらい3年間(=36か月)分の資料を都庁に持参しました。
(3)厚生年金記録照会回答票
東京都で建設業許可を取得する際の特殊性として『実務経験期間の常勤性』を証明しなければなりません。具体的に言うと(2)で「管工事の請求書」+「入金記録」で証明した3年間について、専任技術者は、当該管工事をおこなっていた会社に常勤していなければならないのです。
3年間の実務経験の証明が必要であるのみならず、その3年間の実務経験期間中の常勤性の証明が必要になるわけです。
東京都以外の他の県では、「実務経験証明書(様式第9号)があれば、実務経験証明期間の常勤性の確認資料までは求めない」といったところもあるようですが、東京都の場合は、実務経験証明期間中の常勤性の資料まで提出を求められます。
今回は、専任技術者の方の厚生年金記録照会回答票を年金事務所から取得しました。この厚生年金記録照会回答票には、過去の年金記録が記載されているので、「いつからいつまで」「どこの会社に在籍していたか?」といったことが一目瞭然でわかります。
本事案の場合、大学卒業後の平成15年から、現在の会社に在籍していましたので、実務経験証明期間中(2018年1月~2020年12月)の常勤性についても問題なく証明することができました。
(4)健康保険被保険者証
健康保険被保険者証のコピーも必要です。この健康保険被保険者証は、申請時点で、専任技術者が申請会社に常勤していることの証明として必要になります。
無事、管工事の建設業許可を取得!
上記のように、経営業務管理責任者の(1)(2)の要件をクリアし、専任技術者の要件を証明するための(1)~(4)の資料を準備して都庁に申請に行きました。
無事、管工事の建設業許可を取得することができました。
管工事の建設業許可を取得したいとお考えの人へ
建設業許可を取得するには、「常勤等役員(旧:経営業務管理責任者)」の要件と、「専任技術者」の要件の両方を満たさなければなりません。
今回の事案は、「常勤等役員(旧:経管)」の要件については、それほど、問題はなかったものの、「専任技術者」の要件について、一工夫必要な事案でした。
仮に、「大学の機械科」を卒業した方がいなければ、「10年の実務経験」を証明して建設業許可を取得することになります。この「10年の実務経験の証明」は、決して簡単なものではありません。
できれば「国家資格を持っていること」、国家資格を持っている人がいなければ「指定学科の卒業経歴を持っている人」、「国家資格者」も「指定学科卒業者」も、どちらもいなければ、「10年の実務経験を証明する」といった方法で建設業許可の取得を検討するのが良いと思います。
最後に、弊所で管工事の建設業許可を取得した他のケースを掲載させていただきます。みなさまの参考にして頂ければ幸いです。
| 本店所在地 | 内容 | |
|---|---|---|
|
東京都 墨田区 |
「個人事業主としての3年」と「代表取締役としての2年」の経験を証明し、管工事の許可を取得しました!!
(↑クリックすると、ページが移動します。) |
|
| 本店所在地 | 内容 | |
|---|---|---|
|
東京都 渋谷区 |
「確定申告書+厚生年金被保険者記録照会回答票」の合わせ技1本で10年の実務経験を証明し、東京都建設業許可(管工事)を取得しました!
(↑クリックすると、ページが移動します。) |
|
| 本店所在地 | 内容 | |
|---|---|---|
|
東京都 豊島区 |
実務経験(前の会社+今の会社)10年の証明に成功し、電気工事に管工事を追加しました!!
(↑クリックすると、ページが移動します。) |
|
| 本店所在地 | 内容 | |
|---|---|---|
|
東京都 葛飾区 |
管工事の建設業許可。実務経験10年の証明を無事クリアしました!
(↑クリックすると、ページが移動します。) |
|