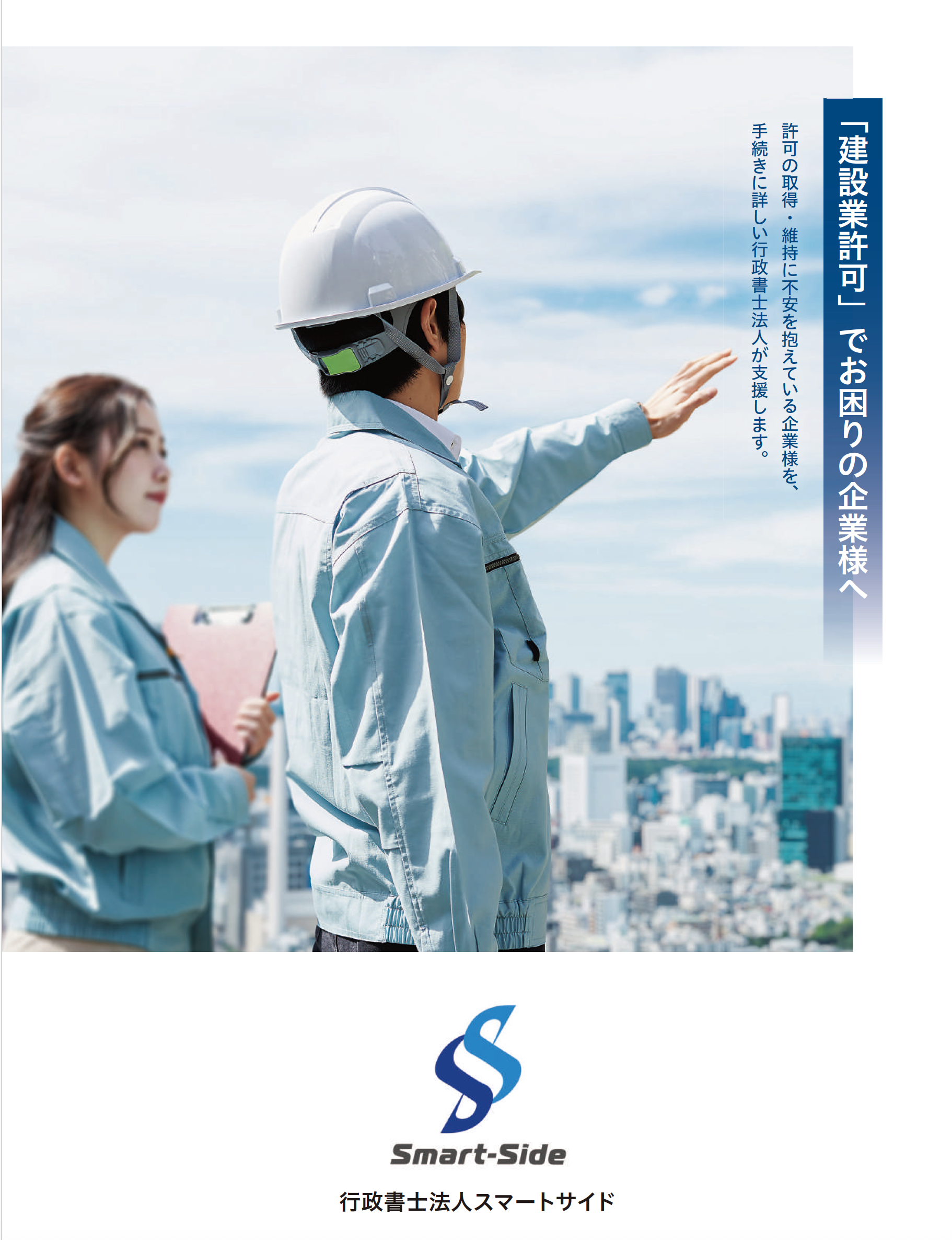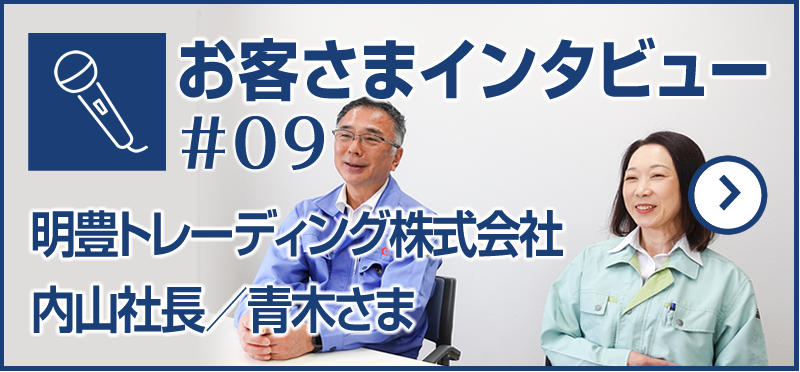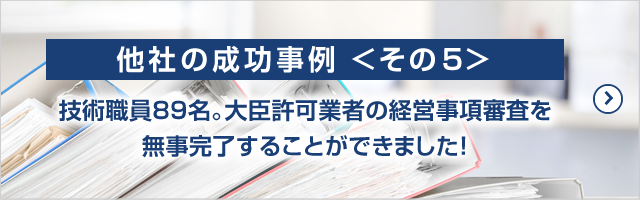
皆さんの中には「経営事項審査を受けてみようと考えている方」や「すでに経営事項審査を受けている方」がいらっしゃると思いますが、
- 経営事項審査は難しい…!
- 経営事項審査ってどうやったらよいのか、わかりにくい…!
- 全体のイメージが理解できないので、とっかかりにくい…!
といった感想をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
規模の大きい建設業者、特に全国に営業所があるような大臣許可業者の場合、技術職員の人数が多ければ多いほど、資料の準備が煩雑で、書類作成が面倒なことになります。
このページでは、「大臣許可業者」でかつ「技術職員の人数が89名の会社」の経営事項審査を無事完了させた弊所の実績とともに、技術職員が多い場合の注意点について、解説をしていきたいと思います。
比較的規模の大きい会社が経審を受ける際の参考になるかと思います。
相談内容:経審手続きを社内担当者から外部の専門家に切り替えたい
概要
| 会社所在地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 業種 | 土木・鋼構造物・しゅんせつ |
相談内容
| 相談内容 | 今までは、社内の担当者に経営事項審査の申請を任せていたが、担当者が高齢になりつつあるので、外部の専門家と協力しながら、手続きを進めていきたい。
まずは、お互いに確認をしあいながら、協力して経審を進めていくことはできないだろうか? |
|---|
申請内容
| 申請内容 |
|
|---|
行政書士法人スマートサイドの対応
まず、打ち合わせの際に、建設業許可の取得状況、経営事項審査の申請状況を確認させていただきました。上記の相談内容に記載した通り、今までは、経営事項審査の申請は、社内の担当者に任せっきりになっていたそうです。
この場合、書類の作成・申請が属人的になり、その担当者が退職した場合や、病気で休職せざるを得なくなった場合に、社内に誰も申請手続についてわかる人がいないといったことになりかねず不安を抱えているようでした。
大臣許可を持っているだけあって、前回申請時点で、技術職員の人数は91名(今回申請時点では、89名)と、とても多い部類に入ります。これを社内の担当者1名で処理するのは大変な労力です。また、万が一、その担当者が退職せざるを得ないような状況になった場合の引き継ぎにも苦労することになると思います。
そういった事情から、先方からは、スマートサイドに依頼するにあたって、初めから全部を丸投げする形ではなく、進捗状況をともに把握し、できれば1つ1つ書類を確認しながら作業を進めたいというご要望がありました。
そこで、
- 進捗については都度、ご報告差し上げること
- 過去の申請状況について不明な点があった場合には、都度、電話での打ち合わせをさせていただくこと
- 弊所で申請した書類について、目を通していただき、申請前にお互いにチェックをしあうこと
などといったいくつかの点の合意を経たうえで、まずは、ご依頼者さまの負担を少しずつ軽くしていくといった方向性で、弊所が、経営事項審査の申請を代行する運びとなりました。
解説:経営事項審査の仕組み
経営事項審査の仕組み
この事案の特徴は、なんといっても「技術職員の人数が89名」と多かったことですが、「技術職員」について記載する前に、大まかな経審の仕組みについて解説したいと思います。
(1)総合評定値(P)の算出方法
経営事項審査は、経営事項審査の結果である総合評定値(P点)を算出するために行います。このP点は、以下の表にあるような、さまざまな審査項目を加味して算出されます。
| 項目区分 | 審査項目 | ||
|---|---|---|---|
| 経営規模等 | 経営規模 | X1 | 完成工事高(業種別) |
| X2 | 自己資本額
利払前税引前償却前利益の額 |
||
| 技術力 | Z | 技術職員数(業種別)
元請完成工事高(業種別) |
|
| その他の審査項目(社会性等) | W | 労働福祉の状況
建設業の営業継続の状況 防災活動への貢献の状況 法令遵守の状況 建設業の経理の状況 研究開発の状況 建設機械の保有の状況 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 |
|
| 経営状況 | 経営状況 | Y | 負債抵抗力
収益性・効率性 財務健全性 絶対的力量 |
| 総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W) |
上の表を見ていただければ、わかると思いますが、経審を受ける会社の「技術職員の人数」は、「技術職員数(業種別)」という審査項目に該当し、経営規模等の技術力=Zとして、評価の対象になります。
このZは、ほかの審査項目であるX1、X2、Y、Wとともに計算式にあてはめられて、経審の結果である総合評定値(P点)の算出に使用されます。
P点(総合評定値)を算出する際のZの割合は25%ですので、ほかの審査項目に比べてウエイトが高く、重要な指標と言えそうです。
そのため、技術職員の人数が多ければ多いほど、経審の点数が上がるという関係性にあります。
(2)技術職員の評点の内訳
一言で「技術者」または「技術職員」といっても、建設業界には、さまざまな技術者資格、国家資格が存在しています。経審ではその資格が一律に評価されるわけではありません。
| 評点 | 技術職員区分資格 | ||
|---|---|---|---|
| 6点 | 1級監理受講者 | 技術者を対象とする国家資格の1級又は技術士法に基づく資格を有し、かつ監理技術者資格者証の交付を受けているもの | |
| 5点 | 1級技術者 | 技術者を対象とする国家資格の1級を有するもの(上記を除く)。技術士法に基づく資格を有するもの(上記を除く)。 | |
| 4点 | 監理技術者補佐 |
監理技術者を補佐する資格を有するもの |
|
| 3点 | 基幹技能者等 | 登録基幹技能者講習の修了証
能力評価基準によりレベル4と判定された者 |
|
| 2点 | 2級技術者 | 能力評価基準によりレベル3と判定された者
技術者を対象とする国家資格の2級を有する者 技能者を対象とする国家資格の1級を有する者 |
|
| 1点 | その他技術者 |
技能者を対象とする国家資格の2級 実務経験による主任技術者 |
|
上の表からもわかるように、より難易度の高い、取得が困難な資格のほうが、点数が高く設定されています。例えば、
- 1級建築施工監理技士(監理技術者証あり、講習受講あり)⇒6点
- 1級土木施工監理技士(監理技術者証なし、講習受講なし)⇒5点
- 1級技士補⇒4点
- 登録電気工事基幹技能者/登録標識・路面標示基幹技能者⇒3点
- 2級建築士⇒2点
- 実務経験10年の主任技術者⇒1点
となっています。
(3)人数が多ければ多いほど、証明資料も多くなる
上記のように、経審の申請の際には
- 技術職員の人数が多ければ多いほど有利
- より難易度の高い国家資格を持っている人が多いほうが有利
といった特徴があります。
例を挙げるまでもないかもしれませんが、
- 実務経験10年の主任技術者が3名しかいない会社
- 1級国家資格を有する技術者が10名いる会社
を比較した場合には、当然、1級国家資格を有する技術者が10名の会社のほうが、Zの点数が有利になり、結果として、より高い総合評定値(P点)を取得できる可能性が高いといえます。
(4)技術職員の常勤性を証明する資料
ここまで、技術職員の資格について説明してきましたが、この技術職員は申請会社に常勤している職員でなければなりません。自分の会社に在籍している技術職員の人数が多いから、経審の点数が上がるわけであって、他社に在籍している職員をカウントすることは(出向の場合を除いて)できません。
この常勤性を証明するには、技術職員名簿を作成するとともに、
- 「審査基準日現在、常勤性の要件を備えており、かつ、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があること」
が必要です。
この常勤性を証明するための資料には、さまざまなものがあるので、手引きを参考によく理解する必要があります。
主な資料として挙げられるのは「健康保険証のコピー」や「健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書」などがあげられます。関東地方整備局に提出する際には「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」も常勤性の資料として認められるようですが、ほかの自治体では認められないところもありますので、申請のまえには、よく確認をしてください。
技術職員が多い場合の資料収集の大変さがお分かりいただけると思いますが、例えば、前述の例でいうと、1級国家資格を有する技術者が10名の会社は、10名分の常勤性の資料を準備しなければならないのに対して、実務経験10年の主任技術者が3名の会社では、3名分の常勤性の資料を準備すれば足りるということになります。
なお、経審の際には、保有する国家資格を証明するための資料(合格証や免許証などのコピー)が必要になることは言うまでもありません。
技術者の人数が多い会社や国家資格保有者の人数が多い会社では、膨大な数の証明資料をそろえることになり、経審の確認資料だけでも、厚さ5~10センチ程度のコピーの枚数になることも少なくありません。
ポイント:技術職員が多い場合の経審の注意点
今回申請したケースの技術職員数の内訳
今回、弊所で対応したお客様は、以下のような技術職員の構成です。
| 評点 | 技術職員区分資格 | ||
|---|---|---|---|
| 6点 | 1級監理受講者 | 21名(講習受講あり) | |
| 5点 | 1級技術者 | 5名(講習受講なし) | |
| 4点 | 監理技術者補佐 |
0名 |
|
| 3点 | 基幹技能者等 |
0名 |
|
| 2点 | 2級技術者 |
36名 |
|
| 1点 | その他技術者 |
27名 |
|
| 合計 | 89名 | ||
国土交通大臣許可を持っていて、営業所が「東京」「千葉」「大阪」「福岡」の4か所にある会社なので、規模感が大きいのが特徴です。
実際に東京都や千葉県の入札に参加し、案件を受注している会社であることから、1級資格者が26名も在籍しています。
以下では、このような技術者の多い会社、規模感の大きい会社、国家資格者の人数が多い会社の申請をするにあたって、注意した点を記載していきます。
申請の際に注意した点
1.技術職員名簿の作成について
申請先自治体によってルールが異なりますが、関東地方整備局管内の大臣許可業者が、経営事項審査を申請する際には、「技術職員名簿」は年齢の若い順に記載する必要があります。
また、技術職員名簿には、生年月日・年齢のほか、
- 業種コード
- 有資格区分コード
- 講習受講の有無
- 監理技術者資格者証交付番号
などを記載する箇所があります。
業種コード
土木工事⇒「01」、鋼構造物工事⇒「11」、しゅんせつ工事⇒「14」といったように決められたコードがあるので、間違いのないように記入しました。
有資格区分コード
有資格区分コードも業種コードと同じように、手引きに掲載があります。有資格区分コードには、「技術者が、どの資格に当てはまるのか」を附番されたコードで記入しなければなりません。
- 一級土木施工管理技士⇒「113」
- 二級土木施工管理技士⇒「214」
- 大学・高校の指定学科卒業経歴+実務経験⇒「001」
- 10年の実務経験⇒「002」
といったように、あらかじめコードが決められているので、間違いのないように記載しました。
講習受講の有無
1級の資格を持っている技術者は、監理技術者証を取得し、かつ、監理技術者講習を受講していると、評点が5点から6点にアップします。そのため、講習を受講している1級資格者については、講習受講の有無の欄に「有り:1」を追記する必要があります。
監理技術者資格者証交付番号
監理技術者資格者証を持っている技術者については、監理技術者資格者証交付番号の記載も必要です。この番号は、監理技術者資格者証を見れば書いてあるので、それを転記するだけですが、11桁もあること、小さい数字で書いてあること、更新の際に番号が変わることなどから、間違いのないように注意して転記をする必要があります。
2.技術職員名簿のほかに必要な名簿
この会社のように技術職員が89名もいると、技術職員名簿の作成だけで、大変な労力をつかうことになりますが、実は、技術職員名簿のほかにも、作成しなければならない技術職員関係の資料というのがあります。
技術職員名簿を作成して「はい。終わり。」ではないわけです。
雇用継続制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号)
技術職員名簿以外に作成しなければならない名簿として「雇用継続制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号)」というのがあります。これは、高年齢者雇用安定法の対象者で、6か月を超える恒常的雇用関係があり、継続雇用制度の適用を受けている技術職員がいる場合に作成する必要があります。
今回の申請では、6名の方が該当していたので、技術職員名簿のほかに、「雇用継続制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号)」も添付して申請しました。
001及び002資格及び099の技術者名簿一覧表(35才未満の技術職員のみ)
この「001及び002資格及び099の技術者名簿一覧表」というのは、技術職員名簿に記載した35才未満の技術職員のうち
- 001⇒指定学科卒業+実務経験
- 002⇒10年の実務経験
- 099⇒その他
の資格コードを記載したものに対して、別途作成が求められる名簿です。
氏名、生年月日のほかに、卒業学校および学科名、経験年数などの記載を求められます。001や002は、特殊な学科を卒業したことや長年の実務経験があることを理由に、経審の加点事由となる資格(コード)なので、一般的な技術職員名簿より詳細に情報の記載を求められています。
今回の申請では15人の方が、該当しましたので、「001及び002資格及び099の技術者名簿一覧表」も添付して申請を行いました。
出向関係を証明する書類
技術職員の中に、出向者がいる場合には、出向証明書など、出向関係を証明できる資料(名簿)の提出も求められます。
技術職員名簿には出向職員は記載できないと勘違いしている方もいらっしゃいますが、出向者でも「出向関係を証明でき、かつ、6か月を超える常勤性を証明できる場合」には、技術職員名簿に掲載することができ、経審の加点事由になります。
なお、関東地方整備局の手引きには、以下の通り記載があるので、こちらも確認してみてください。
出向先で常勤であれば、出向先の職員として評価の対象となる。出向協定書・出向証明書には、最低限、次の内容が定められていることが必要になる。
- 出向期間(6か月を超える常勤性が確認できるもの)
- 出向者の身分保障及び指揮監督権について
- 出向者への給与支払い及び社会保険料負担、出向料について
今回の申請では、5名の方が出向者に該当しましたので、出向契約書のほか、出向者への給料の支払いがわかる資料などを添付して申請しました。
経審でお困りの際は、行政書士法人スマートサイドへ
以上のように、技術者の人数が多いと、技術職員名簿の作成が大変な作業になるばかりでなく、
- 雇用継続制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号)
- 001及び002資格及び099の技術者名簿一覧表
- 出向関係を証明する書類
なども用意しなければならないため、経審を受けるための準備に、膨大な作業時間と労力を費やすことになります。
また、関東地方整備局の手引きにも記載があることですが、技術職員の合格証・資格証のコピーについては、1人の技術者ごとに、技術職員名簿の順番に①合格証、②監理技術者資格者証、③監理技術者講習修了証の順番にそろえて提出するように注意書きがあります。
新たな技術職員の入社や、退職、資格証の5年の有効期間の管理などを考慮すると、技術職員名簿の作成が、どれだけ困難で大変な作業かがお分かりいただけるかと思います。
弊所の申請実績を記載したこのページが、技術職員の多い会社が、経審を受審する際の参考になれば幸いです。なお、行政書士法人スマートサイドでは、技術職員の人数が多い会社の経審にも対応しております。
お困りの際は、まずは、問い合わせフォームからご連絡をください。