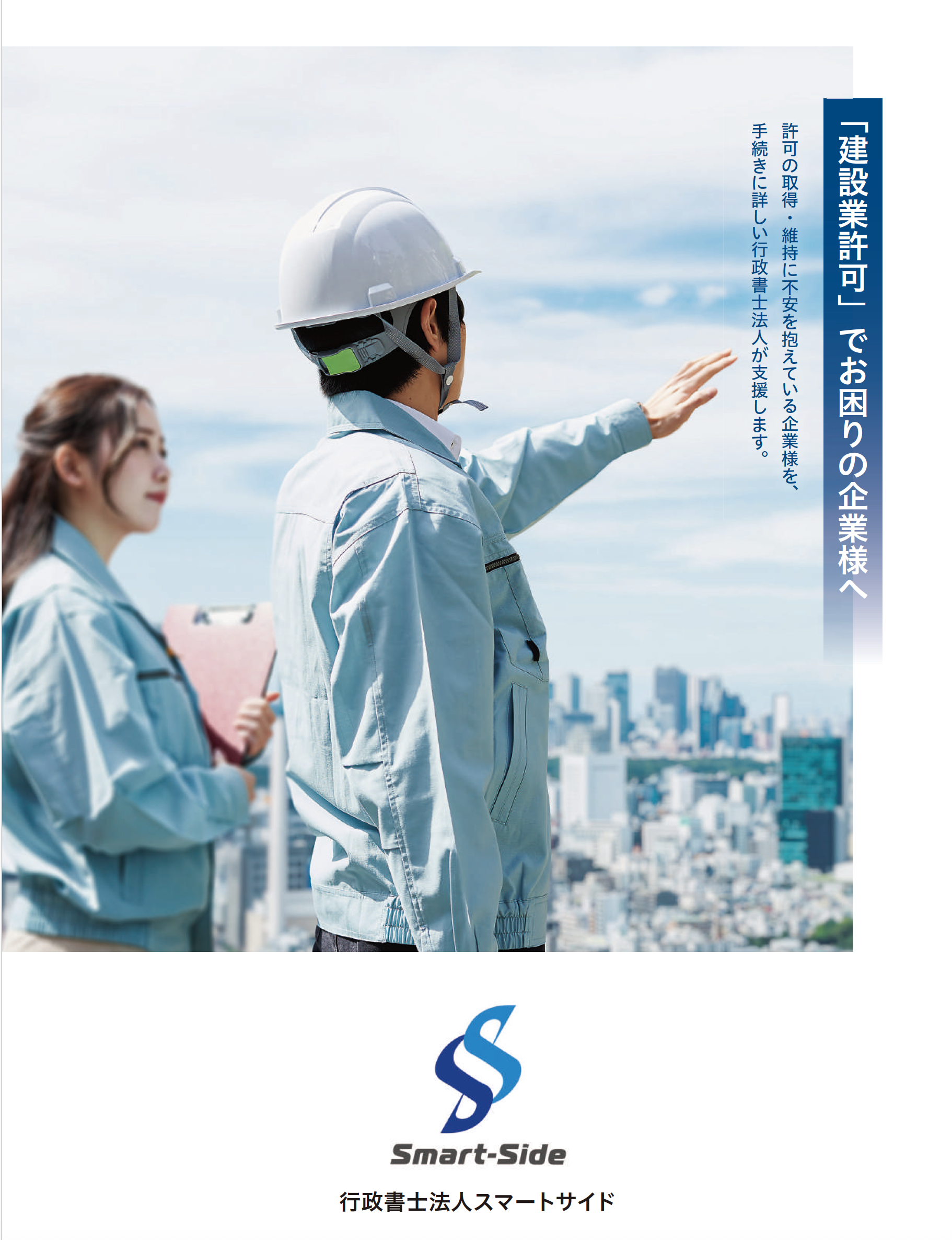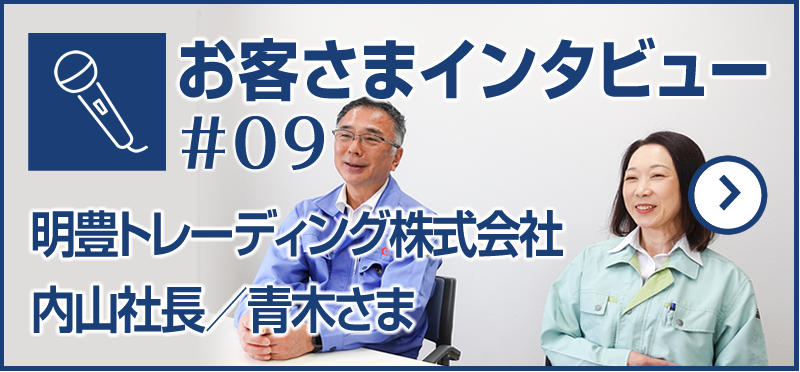東京都の建設業許可を取得・維持する専門家。大規模な会社の許可申請や、複雑な事案での許可維持を数多くサポート。とくに「経営業務管理責任者の要件の証明」や、「営業所技術者の実務経験の証明」において、困難な状況にある会社を数多く支援してきた実績があり、お客さまからの信頼も厚い。「建設会社の社長が読む手続きの本(第2版)」を出版。 インタビューは、こちら。
弊所には、建設業許可の取得を検討しているお客さまからの
「常勤」とは、原則として、本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。文章に記載すると、ちょっと難しいですが、要は「一般的に勤務しているという実態があって、その勤務実態が、社会人としての常識的な範囲であること」といった表現になります。これはあくまでも社会一般的な解釈ですが、通常であれば、9-17時くらいの勤務が常識的な範囲にあたると思われます。ですので、「1日3時間、週2日の勤務」では常勤性があるとは言い難いです。
そうすると、当然のことながら、経営業務管理責任者や営業所技術者に支払っている給料が数万円程度だと、常勤性を証明できそうにありません。仮に「9-17時で会社で働いているのに、給料が5万円」だとしたら、法解釈や制度ではなく、一般常識に照らし合せて、「名義を借りているだけです」といっているのに等しいです。これでは、到底、建設業許可を取得できるはずがありません。
建設業許可を取得する際には、「経営業務管理責任者や営業所技術者が、会社に常勤しています」と口頭で申し伝えるだけでは、足りません。裏付資料(書類)を使って、常勤性を証明して行く必要があるのですが、一体、どういった書類を準備すればよいのでしょうか?
以前までは、東京都の建設業許可を取得するにあたって、経管・営技の住民票の提出は必須でした。現在では、住民票の提出は必要ありません。しかし、経営業務管理責任者や営業所技術者が「どこに住んでいるのか?」「住民票上の住所がどこにあるのか?」といったことは、常勤性を考えるうえで、切っても切り離せません。そのため、住民票の提出が省略されたとしても、やはり、経管や営技の住民票上の住所は、許可を取得するうえで、とても重要であることに変わりありません。
たとえば、会社が新宿区にあり、経営業務管理責任者と営業所技術者の住民票の住所が渋谷区だった場合。毎日所定の時間に会社に来て勤務していると考えられるのが一般的なので、会社に常勤しているという実態が証明でき、常勤性が推定されます。これは、とくに問題のないパターンです。
2.住民票上の住所からの通勤時間が、片道2時間程度のケース
では、経営業務管理責任者や営業所技術者の住民票の住所が遠隔地(例えば、通勤時間がおおむね片道2時間を超える)の場合は、どうでしょう。仮に、経営業務管理責任者や営業所技術者の住民票の提出が必要なくなったとはいえ、「経営業務管理責任者の略歴書」や「営業所技術者の証明書」といった書類には、住所を記載する箇所があります。そのため、住民票上の住所が、「まったくどこでもよい」ということではないのです。この場合は、「住民票上の住所から会社に通えないことはないけど、毎日片道2時間かけて本当に通勤しているのですか?」といった疑義が生じます。そこで、こういった疑念を晴らすためにも、確認資料として「電車通勤なら定期券のコピー」「自動車通勤ならETCの通行記録」やなどを提出していました。
片道2時間程度の通勤時間がかかるとしても、「定期を6か月分購入している」ということであれば、「毎日、確かに通勤して会社に勤務している(常勤している)」といった推測が成り立つわけです。また、「ETCの通行記録のほかに、会社近くの駐車場の賃貸借契約書」があれば、「自動車で毎日会社まで通勤している」といえ、常勤性を証明することもできます。
弊所では、実際に「定期券のコピー」や「ETCの通行記録のコピー」を提出して、東京都の建設業許可を取得したことがあるので、皆さんも、確認してみてください。
3.住民票上の住所が、さらに通勤困難な「地方」だったケース
では、経営業務管理責任者や営業所技術者の住民票の住所が「関西」や「四国」「東北」など、東京への毎日の通勤といった勤務形態が常識的ではない場合、はどうでしょう?強いていえば、通勤に2時間以上かかるようなケースです。
この場合、「青森県から毎日東京に通勤しています」という主張はどうみても一般的ではないです。むしろ「住民票の住所は『青森』ですが、東京で部屋を借りて、そこ(東京都内のマンション・アパート)から会社に出勤しています」という実態があるのではないでしょうか?そこで、こういった場合には、東京都内のマンション・アパート・社宅に生活の実態があることを証明するために、東京都内のマンション・アパート・社宅の「賃貸借契約書」や「賃料・家賃の領収書」「経営業務管理責任者や営業所技術者あての郵便物」を資料に、実際に『そこ(東京都内)に住んでいます』といったことを証明しました。
『実際にそこ(東京都内)に住んでいる』のであれば、「会社への毎日の通勤も不可能ではなく、常勤性が推定される」という判断が成り立ち、常勤性を満たし、許可を取得することができるようになります。
1.マイナンバーカード(もしくは資格確認書)
法人の事業者の場合、健康保険への加入は義務付けられています。これは法律上の義務なので、かならず加入していただかなくてはなりません。そのため、令和7年11月までは、法人名や事業所名が記載されている健康保険被保険者証のコピーの提示が求められていました。これによって、経営業務管理責任者・営業所技術者が当該法人に所属し、勤務していることの実態を証明できたわけです。
しかし、令和7年12月以降、健康保険証の使用は廃止され、マイナンバーカード(マイナ保険証)の提示に切り替わりました。今までは、健康保険証の提示でよかったのが、マイナ保険証の提示が必要になると、運用が変わったのです。(なお、マイナンバーカードを持っていない人は「資格確認書」の提示が必要になります)。
もっとも、マイナンバーカードにも資格確認証にも「事業所名・法人名」は記載されていません。そのため、令和7年12月以降は、常勤性を証明するために、別途、以下のような書類の準備が必要になりました。
2.標準報酬決定通知書
みなさんの会社には、「健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬決定通知書」が年金事務所から送られてきていると思います。この標準報酬決定通知書は、健康保険料や厚生年金保険料の決定通知書なので、必ず会社に届いているはずなので、確認をしてみてください。会社を立ち上げて間もない場合、もしくは経営業務管理責任者や営業所技術者が会社に入社してすぐの場合には、標準報酬決定通知書がなかったり、標準報酬決定通知書に名前の記載がなかったりします。その場合には、健康保険や厚生年金保険の被保険者の資格を取得したことの証明になる健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認書があれば、常勤性を証明することができます。
なお、2つ以上の会社から給料が払われているような人は、注意が必要です。
- A社から30万円の給料が支払われている
- B社から100万円の給料が支払われている
ようなケースにおいて、「A社に常勤している」という主張は、難しいのではないかと思います。以下の動画で詳しく解説していますので、2つ以上の会社から給料や役員報酬が支払われている場合には、参考にしてみてください。
(YouTube動画のご案内)
令和7年12月から「健康保険証」の廃止に伴い、常勤性の確認資料に、大きな変更がありました。この動画では、2つ以上の会社から給料をもらっている人を対象に「標準報酬決定通知書」を提出することのリスクについて解説しています。手引きに「標準報酬決定通知書」と書いてあるからと言って、「標準報酬決定通知書」を提出すると、かえって経管・営技の常勤性に疑義が生じる場合があることを事前にご理解いただきたいという注意喚起も込めています。
2.住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
こういった場合には、住民税の特別徴収税額通知書(徴収義務者用)が、常勤性を証明する書類になります。
地方税法上、所得税を源泉徴収している事業主(≒月額88.000円以上の給料を支払っている事業主)については、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。まさか、経営業務管理責任者や営業所技術者に常勤してもらっているのに、月々の給料が88.000円未満ってことはないはずです。仮に経管・営技が、75才以上で健康保険に加入することができず、標準報酬決定通知書を常勤性の資料として提出することができなかったとしても、「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)」を提出することはできるはずです。
仮に、いままで普通徴収であった場合には、特別徴収への切替届(異動届)を提出することによって、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)に変えることができますので、「会社に常勤で働いてもらっているのに、住民税の特別徴収に関する証明資料を出せない」ということは、通常ありないと思います。
3.確定申告書
上記のように、経営業務管理責任者や営業所技術者の常勤性を証明するために、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)や特別徴収への切替届(異動届)を出すことができないということは、一般的にはないと思うのですが、「事業所の総従業員数が2人以下の場合」や「事業専従者(個人事業主)の場合」には普通徴収も認められているようです。
この場合には、住民税の特別徴収に関する資料を常勤性の資料として提出することができないため、確定申告書を用いて常勤性を証明するしかありません。
法人の場合には、役員報酬明細を確認します。法人の役員として常勤しているのであれば、それ相応の役員報酬が記載されているはずですし、「常勤」の箇所にチェックが入っているはずです。個人の場合には、第一表と第二表を確認します。個人事業主として相応の所得を得ているか、給与所得がないか(給与所得があるということは他の会社から給料をもらっているということなので常勤性が認められない可能性があります)などを確認します。
以上、かなり細かいとこまで記載してきましたが、上記のように、建設業許可を取得するにあたって、経営業務管理責任者や営業所技術者の常勤性をごまかすことはできません。弊所にお問合せを頂くお客様のなかには、「どうしても建設業許可を取得しなければならない」というご相談が多く寄せられます。
しかし、上記にあげた、「マイナンバーカード(もしくは資格確認書)」「標準報酬決定通知書」「住民税特別徴収額通知書」「確定申告書」は、いずれも公的な書類です。これらの書類を自分の都合の良いように書き換えることは不可能であり、経営業務管理責任者や営業所技術者が常勤していないのに、あたかも常勤しているかのような書類を準備することは法律上許されないのです。
とはいうものの、
■ 本当にこの書類でよいのか?
■ 現在ある資料で、建設業許可を取得することができるのか?
■ 社長や役員が常勤性を満たしているかわからない?
■ 経管・営技の要件について、きちんと確認したい
という人もいらっしゃるかもしれません。そんなときは、ぜび、弊所にご連絡ください。
このページで見てきたように、建設業許可の取得は、手引きに記載されている書類を揃えるだけでは不十分です。東京都の厳しい審査に通るためには、実態に即した適切な証明資料の準備が不可欠です。
(事前予約制の有料相談のご案内)
私たち行政書士法人スマートサイドは、建設業許可を取得する手続きにおいて、東京都内でも有数の実績があります。豊富な経験と専門的な知識をもとに、御社の建設業許可の取得を強力にサポートします。弊所に事前予約制の有料相談をお申込みいただければ、許可要件の事前確認から、最適な証明資料の整備、申請手続きのポイントまで、的確なアドバイスを提供します。ネット上の無料情報では不十分なことが多く、誤った知識によって申請が遅れたり、許可が下りなかったりするケースも珍しくありません。だからこそ、確実な知識と許可取得の方法を知るためには、有料での相談をおすすめします。
相談者一人一人への適切な対応、および、質の高い面談時間の確保の見地から、相談は有料とさせていただいておりますが、1時間 11,000円 の個別相談では、御社の経営業務管理責任者・営業所技術者の在籍状況に合わせた具体的なアドバイスを行い、最短で許可を取得するための最適な道筋を示します。
✅ 間違いのない方法で、確実に許可を取りたい
✅ 建設業許可のプロに相談し、最良の選択をしたい
そうお考えの方は、ぜひ 行政書士法人スマートサイド へ有料相談をご活用ください。