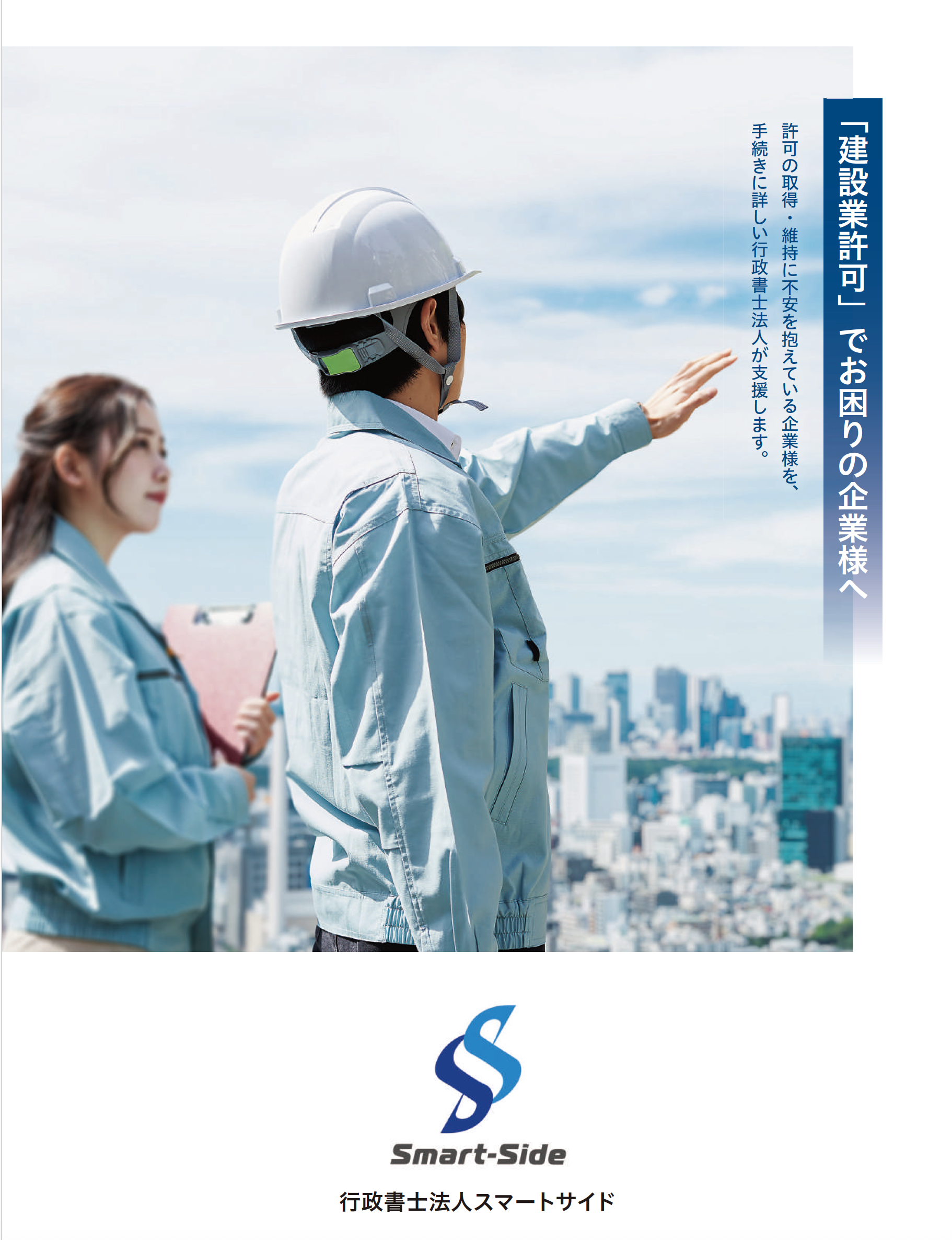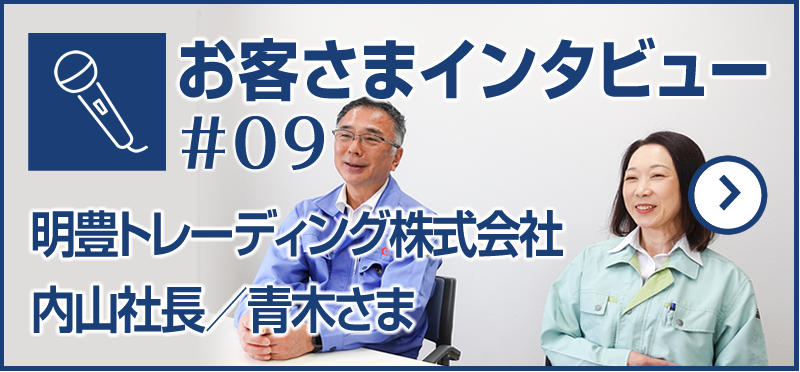■ 建設業許可を持っている会社を吸収合併する
■ 建設業部門を切り離して、子会社に建設業許可を承継させたい
■ 建設工事部門を他社に「売却すること」を検討している
という人はいらっしゃいませんか?「合併・分割・事業譲渡」をまとめて事業承継といいますが、ただ単に事業を承継したからと言って、建設業許可が新しい会社に「くっついてくる」わけではありません。それどころか、何もしないでいると、建設業許可はいったん取り下げ(廃業)となり、新しい会社で新規で取得しなおさなければなりません。
せっかく「建設業許可を持っている会社を合併する」「子会社を設立して建設業許可を引き継がせたい」「他社に部門ごと売却する」のに、いまある建設業許可の番号や建設業許可業者の地位を承継できないのでは、事業承継の意味がありませんね。あまり知られていませんが、このようなケースにおいて、建設業許可を承継(継続)させるには、事業承継日よりも前に「認可申請」を行い「認可」を受ける必要があるのです。
そこで、このページでは、建設業許可の取得・維持の専門家である行政書士法人スマートサイド代表の横内賢郎が「建設業許可の事業承継(合併・分割・譲渡)に伴う認可申請手続きで気を付けるポイント」について、わかりやすく解説していきたいと思います。

東京都の建設業許可を取得・維持する専門家。大規模な会社の許可申請や、複雑な事案での許可維持を数多くサポート。「大臣許可会社の新設分割に伴う許可承継」「親会社の子会社合併に伴う許可の維持」を経験するなど、事業承継における認可申請手続きにも精通している。「建設会社の社長が読む手続きの本(第2版)」を出版。 インタビューは、こちら。
【1】建設業許可の事業承継の手続きの流れ
「合併・分割・事業譲渡」といった事業承継の際に、承継先に「建設業許可番号」や「建設業者たる地位」を引き継がせる(引き継いでもらう)ためには、以下のような流れに沿って、認可手続きをすることが必要です。
1.事前相談
まずは、許可行政庁への事前相談が必要です。この相談は、「この先どういったスケジュールで事業承継(合併・分割・事業譲渡)がなされるのか?」を明確にし、「いつまでにどんな書類(手続き)をする必要があるのか?」を共有するためです。たとえば、極端な話をすると、「来週、会社を合併します」と言っても、建設業許可を引き継ぐことはできません。
建設業許可を引き継ぐには、事前相談を行ったうえで、認可申請をし、さらに認可を受けるという手順を踏む必要があるからです。そのために、許可行政庁への事前相談は、なるべく早めにおこなった方がよいというのが、専門家としての私の見解です。
![]()
2.認可申請
続いて、認可申請をする必要があります。では、認可申請とはいったいどんな申請なのでしょうか?
簡単に言うと「これから建設業許可を持っている会社を合併します。ついては、この会社が持っている建設業者としての地位や建設業許可番号を引き継がせてください」という旨の申請です。会社の分割の場合には、「これから会社を分割しますので、建設業許可の番号および建設業許可会社としての地位を、分割先の新しい会社に引き継ぎますので、よろしくお願いします」といった感じです。
建設業許可の「許可申請」や「更新申請」については、聞きなじみがあると思いますが「認可」という言葉は、あまり聞き慣れない言葉かもしれません。要は「建設業許可の引継ぎをさせてください。今までと同じ許可番号を使わせてほしいです」という旨の申請というようにとらえて頂ければと思います。
注意が必要なのは、この認可申請には期限があるということです。東京都の手引きには認可申請の受付期間は「承継予定日の閉庁日を含まない前日の2か月から25日前まで」となっており、関東地方整備局の手引きには「承継予定日の90日前まで」となっています。このように、いつまでに認可申請を行わなければならないか?というのは、許可行政庁によってバラバラです。また、上記、期間を過ぎると、認可申請を受け付けてくれない場合もあります。
そのためにも、事業承継が決まったら、できるだけ早めに「1.事前相談」を行い、許可行政庁とスケジュールの調整を行うとよいと思います。
![]()
3.認可
認可申請が無事、受理されると審査が始まります。認可申請は「会社と会社の合併」や「会社の分割」といった会社組織の大きな再編を伴う手続きです。そのため、通常の許可申請や更新申請と比べて、審査にも時間がかかる印象です。東京都の場合、承継予定日の1週間程度前に申請者宛てに「認可通知書」が郵送されます。
ここでも注意が必要なのは、「認可は、事業承継日よりも前に受けていなければならない」という点です。たとえば、「会社の合併後に、合併元が持っていた建設業許可を引き継ぎたい」といっても遅いのです。ここまで、記載した「1.事前相談」「2.認可申請」「3.認可」はすべて、事業承継の日よりも前に終わっていなければなりません。
![]()
4.後日提出書類
認可の手続きで厄介なのが、事業承継後に提出しなければならない書類(「後日提出書類」という)がある点です。通常の建設業許可の新規申請や建設業許可の更新の場合、申請後や許可取得後に提出しなければならない書類はありません。しかし、認可の場合、必ず後日提出書類の提出が必要になります。
これは、「合併」「分割」といった事業承継の性質からくるものです。例えば、A社とB社が合併してC社になったとしましょう。この場合、C社に関する「登記簿謄本」や「社会保険に関する書類」は、合併後にならないと取得できません。A社とB社が合併してC社が建設業許可を引き継ぐことになった場合、C社に関する書類は、C社設立後、つまり事業承継の後にならないと取得できないので、認可のあとに、改めて、C社に関する書類を「後日提出書類」として提出する必要が出てくるのです。
この後日提出書類には新会社の「登記事項証明書」のほか「都税事務所(または税務署への)法人設立届」や「法人番号を証明する資料」や「社会保険の加入資料」などがあげられます。
【2】建設業許可を引き継ぐために必要な書類
建設会社の「合併・分割・事業譲渡」の際に、建設業許可を承継するために必要な書類は以下のように「認可申請時に提出するもの」と「事業承継日以降に提出するもの(後日提出書類)」の2つに分けて考える必要があります(※なお、このページでは、東京都都市整備局市街地建築部建設業課が発行する「令和7年度 建設業許可申請の手引き」を参考に、書類を掲載しています)。
認可申請時に提出するもの
(本冊)
| 書類 | 詳細 |
|---|---|
| 譲渡/合併/分割認可申請書 | 申請書の表紙に該当するもの |
| 役員等の一覧表 | 認可を受ける会社の役員に関する一覧表 |
| 営業所一覧表 | 認可を受ける会社の営業所に関する一覧表 |
| 営業所技術者等一覧表 | 認可を受ける会社の営業所技術者に関する一覧表 |
| 工事経歴書 | 認可を受ける会社のもの |
| 直前3年の工事施工金額 | 認可を受ける会社のもの |
| 使用人数 | 認可を受ける会社のもの |
| 誓約書 | 認可を受ける会社のもの |
| 定款 | 新規設立法人である場合は後日提出可 |
| 営業の沿革 | 新規設立法人である場合は後日提出可 |
| 所属建設業者団体 | 新規設立法人である場合は後日提出可 |
| 健康保険等の加入状況 | いずれか一方 |
| 健康保険等の加入状況に関する誓約書 | |
| 主要取引金融機関名 | 新規設立法人である場合は後日提出可 |
(別とじ)
| 書類 | 詳細 |
|---|---|
| 常勤役員等証明書 | 認可を受ける会社の常勤役員に関する証明書 |
| 常勤役員等略歴書 | 認可を受ける会社の常勤役員に関する略歴書 |
| 営業所技術者等証明書 | 認可を受ける会社の営業所技術者に関する証明書 |
| 技術者要件を証明する資料 | 合格書や卒業証書や実務経験証明書 |
| 許可申請者の住所、生年月日の調書 | 認可を受ける会社の役員等に関する調書 |
| 株主調書 | 認可を受ける会社の株主等に関する調書 |
| 登記事項証明書 | 新規設立法人である場合は後日提出可 |
| 事業税の納税証明書 | 新規設立法人である場合は設立届を後日提出可 |
(確認資料)
| 書類 | 詳細 |
|---|---|
| 承継に関する書類 | 合併・分割・事業譲渡に関する契約書や説明書など |
| 登記されていないことの証明書 | 発行後3か月以内 |
| 身分証明書 | 発行後3か月以内 |
| 常勤役員等の確認資料 | 常勤性の確認資料は後日提出 |
| 営業所技術者等の確認資料 | 常勤性の確認資料は後日提出 |
| 社会保険の加入証明資料 | 新規設立法人である場合は後日提出可 |
| 法人番号を証明する資料 | 新規設立法人である場合は後日提出可 |
| 営業所の確認資料 | 新規設立法人である場合は後日提出可 |
| 役員等氏名一覧表 | 認可を受ける会社の役員等の一覧表 |
承継日後に提出するもの(後日提出書類)
| 書類 | 詳細 |
|---|---|
| 定款 | 新規設立法人である場合、30日以内に提出 |
| 承継直後の財務諸表 | 新規設立法人である場合、30日以内に提出 |
| 営業の沿革 | 新規設立法人である場合、30日以内に提出 |
| 所属建設業者団体 | 新規設立法人である場合、30日以内に提出 |
| 主要取引金融機関名 | 新規設立法人である場合、30日以内に提出 |
| 法人設立届 | 新規設立法人である場合、30日以内に提出 |
| 法人番号を証明する資料 | 新規設立法人である場合、30日以内に提出 |
| 承継日における経管・営技の常勤性の確認資料 | 承継後、2週間以内に提出 |
| 健康保険の加入状況 | 承継後、2週間以内に提出 |
| 社会保険の加入証明資料 | 承継後、2週間以内に提出 |
| 営業所の確認資料 | 承継後、2週間以内に提出 |
| 被承継者の決算報告 | 被承継者の事業年度終了後4か月以内 |
| 大臣認可に係る届出書 | 知事許可業者が大臣認可を受ける場合 |
また、後日提出書類の提出期限が「30日以内」「2週間以内」といったように、とてもタイトに設定されています。合併や分割によって、新しい法人が設立された場合、法人設立の登記が完了するまでに1か月以上かかるという話をよく聞きます。そのため、法人設立届や社会保険の加入証明資料を期限内に提出することができないケースもあります。そういった場合には、行政庁に連絡をし、事前に事情を説明するようにしてください。
【3】認可申請の際に気を付けるポイント
ここまで、「建設業許可の事業承継(合併・分割・譲渡)に伴う認可申請の手続きの流れ」を見てきましたが、手続きを進めるにおいて、気を付けるべき注意点があります。
1.「認可申請」および「認可」は、事業承継よりも前
手続きの流れと重複しますが、「認可申請」および「認可」は、事業承継よりも前に終わっていなければなりません。「合併」「分割」「事業譲渡」が終わってから、「建設業許可を引き継ぎたい」と言っても手遅れです。「建設業許可の番号」や「建設業許可会社としての地位」を引き継ぎたい場合には、必ず事業承継日よりも前に、認可申請を行い認可を受けておくようにしましょう。
2.「経管」「営技」の常勤性を切らさないこと
建設業許可の取得のみならず、建設業許可の維持についても、「経管」「営技」の常勤性は必須です(なお「経管」「営技」の常勤性については、『経営業務管理責任者と営業所技術者の「常勤性の確認資料」を専門家が解説』というページでも詳しく解説していますので、興味のある方は、ご参照ください)。これと同じように事業承継においても「経管」「営技」の常勤性を切らしてしまうと、建設業許可を維持することができません。以下、2つの事例をもとに見ていきます。
(事例1:承継前に退職)
たとえば、建設業許可を持っているA社が、会社分割によって、子会社であるB社を設立し、その子会社(B社)に建設業許可を引き継がせようとする場合。建設業許可を持っているA社の「経管」「営技」は、会社分割とともに子会社であるB社に移籍しなければなりません。そうであるにも関わらず、「会社分割前に経管が退職してしまった」とか「会社分割よりも前に営技が会社を辞めてしまった」ということだと、「経管」「営技」の常勤性が認められず、建設業許可の要件を満たしていることにはなりません。
このように、承継前に許可要件である「経管」「営技」が退職してしまうと、許可を承継することができないので注意しましょう。
(事例2:社保加入の日付が問題)
たとえば、建設業許可を持っているC社を、D社が吸収合併したとします。吸収合併の日付は4月1日です。にもかかわらず、C社の「経管」「営技」であったXさんがD社の社会保険に加入した日が4月10日だった場合はどうでしょう。D社はC社の許可を4月1日付けで引き継ぐわけですから4月1日時点で、許可要件を満たしていなければなりません。そうであるにもかかわらず、XさんのD社の社保加入日が4月10日だった場合、4月2日~4月9日までの間、D社には「経管」「営技」のXさんが常勤しておらず、許可要件を満たしていない期間が発生してしまいます。
このような場合には、認可は取り消され、建設業許可を引き継ぐことができません。
以上のように、事業承継の前後において、建設業許可の要件である「経管」「営技」の常勤性を維持しなければならない点に注意が必要です。
3.後日提出書類の提出期限について
手続きの流れでも説明したように「認可」を受けて「事業承継」が行われたあとに「後日提出書類」の提出が必要になります。この「後日提出書類」の提出期限にも定めがあります。東京都の場合は、承継後30日以内とされています(書類によっては2週間以内)。ですが、合併や分割といった組織再編の場合、新しい会社の登記簿謄本が出来上がってくるのに1か月以上かかる場合もあるため、承継後30日以内に、各種書類を取り揃え、東京都に提出するのが、事実上不可能といった場合も出てきます。
そういった場合には、事前に東京都に連絡を入れて、進捗状況を説明するなど工夫をしてみてください。なお、東京都の手引きには、「法令で定められた期限以内に提出がされない場合、事前認可の取消処分の対象となる」とありますので、提出し忘れや、提出漏れについては、くれぐれも注意するようにしてください。
4.建設業許可の業種を承継することができない場合
以下の事例1、事例2で説明するように、必ずしも希望通りに許可業種を承継することができないケースがあります。
(事例1:同一の業種で「般」「特」が重複するケース)
下の図は、「建設業許可を持っているB社」が「建設業許可を持っているA社」を吸収合併するケースです。
| A社(吸収合併消滅会社) | B社(吸収合併存続会社) |
|---|---|
| 土木(特定) 舗装(一般) 造園(一般) 鉄筋(特定) |
建築(特定) 大工(一般) 左官(一般) 鉄筋(一般) |
鉄筋工事の業種で、A社は(一般)を、B社は(特定)を持っています。建設業許可においては、同一業種で(一般)(特定)の両方を持つことはできないことになっています。そのため、B社がA社の「鉄筋(特定)」を承継したいと考えた場合、認可申請まえに、あらかじめB社の「鉄筋(一般)」を廃業しておく必要があります。
| 吸収合併後のB社 |
|---|
| 土木(特定)・建築(特定) 舗装(一般)・大工(一般) 造園(一般)・左官(一般) 鉄筋(特定) |
こうすることによって、吸収合併後のB社は、A社の「鉄筋(特定)」を引き継ぐことができるようになるわけです。
(事例2:許可業種の一部のみの承継は不可)
事業承継という性質上、許可業種の一部のみの業種を承継することはできません。たとえば、建設業許可を持っていないD社が、建設業許可を持っているC社を吸収合併するような以下のケースです。
| C社(吸収合併消滅会社) | D社(吸収合併存続会社) |
|---|---|
| 建築(特定) 土木(特定) 造園(一般) |
建設業許可なし |
この場合、D社はC社を吸収合併するにあたって、「建築(特定)」「土木(特定)」「造園(一般)」のすべてを承継しなければなりません。仮にD社が「うちの会社は造園工事はしないので、造園工事業は承継しなくて大丈夫です」といったとしても、「建築(特定)」「土木(特定)」のみを承継することはできず、3業種すべてを承継する必要があります。
どうしても「造園(一般)」は必要ないというのであれば、認可申請前にC社が「造園(一般)」を廃業しておくか、とりあえず承継をしたうえで、承継後にD社が「造園(一般)」を廃業する必要があります。
5.大臣許可業者が知事許可業者になる場合
複数の支店をもつ大臣許可業者が、会社分割を行い1つの支店(=新しく設立した会社)に許可を承継させる場合、認可申請だけでなく許可換え新規申請が必要になるケースがあります。
たとえば、山梨本店・東京支店の国土交通大臣許可の業者が、会社分割し、山梨本店では建設業を行わず、新会社である東京支店に許可を引き継がせる場合。新会社は大臣許可ではなく、東京都知事許可になります。このようなケースにおいては、認可申請と合わせて、大臣許可から都知事許可に変更するための許可換え新規申請が必要になります。
| E社(大臣許可業者) | |
|---|---|
| 山梨本店 | 東京支店 |
認可申請をするだけでは、関東地方整備局から東京都庁に許可情報が引き継がれないため、国土交通大臣許可から東京都知事許可に切り替えるための(許可換え新規)手続きが必要になるのです。
| E社 | 新設会社(東京支店) |
|---|---|
| 建設業許可なし | 都知事許可 |
【4】建設業許可承継の専門家インタビュー
「合併・分割・事業譲渡」などの事業承継後にも、従前の建設業許可を承継する際の注意点については、こちらのインタビュー記事でも詳しく解説しています。
行政書士法人スマートサイド代表の横内が「建設業許可を引き継ぐには?」「認可申請の際に必要な書類は?」「合併・分割・事業譲渡における建設業許可承継の具体例」について、インタビュー形式で詳しくお答えしています。
事業承継を検討しているという人は、ぜひ、こちらのインタビュー記事も参考にしてみてください。
【5】建設業許可の合併・分割・事業譲渡でお困りの際は

建設業許可の事業承継(合併・分割・事業譲渡)の際に、「許可番号を継続し、許可会社としての地位を引き継ぐには、どのような手続きが必要で、どういった点に気を付けるべきか」という視点から、説明してきましたが、いかがでしたでしょうか?
国の統計によると、令和6年度の事業承継の認可件数は1060件となっており、その内訳は譲渡及び譲受け868件、合併78件、分割43件、相続71件ととても少ない割合となっています(参照:【国土交通省公式】建設業許可業者数調査の結果概要(令和7年3月末現在))。
| 認可総件数 | 1060件 |
|---|---|
| 譲渡及び譲受け | 868件 |
| 合併 | 78件 |
| 分割 | 43件 |
| 相続 | 71件 |
認可制度は、令和2年10月の建設業法改正で新たに制度化された手続きです。認可総件数が年間1000件程度と、少ないのは、建設会社の合併や分割やM&Aが業界内に浸透していないことが要因として考えられるかもしれません。しかし、建設業界の人手不足や後継者不足は、深刻化しており、建設業許可を維持できずに廃業していく会社も増加しつつあります。
私たち行政書士法人スマートサイドは、建設業許可取得や維持の専門家として、長年にわたり建設会社のサポートを中心に活動してきました。新規申請や更新申請、変更届の提出はもちろんのこと、合併・分割・事業譲渡の際の認可申請においても、力になりたいと考えています。実際、会社分割や合併に関する相談は増えつつあります。
(事前予約制の有料相談のご案内)
弊所では、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の確保という見地から、初回に限り1時間11,000円の相談料を頂戴しております。この事前予約制の有料相談では、
■ 事業承継の事前相談から認可申請までのスケジュールの共有
■ 必要書類の準備のポイント
■ 御社の状況に応じた申請書類の作成方法の打合せ
など、さまざまな情報を共有し、御社にとって、一番最適でストレスのない認可申請手続きを実現する方法を一緒に検討していくことができます。もし、事業承継や認可申請で、建設業許可を承継したいとお考えの人は、行政書士法人スマートサイドに事前予約制の有料相談をお申込みください。